目次
第一部 集中定数系の振動制御
第1章 振動制御
1 振動現象
2 振動制御の分類
3 振動制御の応用例
第2章 受動方式による振動制御
1 受動ダンパの基本構成
2 フラムダンパ(ダイナミックアブゾーバ)
3 ダイナミックダンパ(動吸振器)
4 振動絶縁
第3章 準能動方式による振動制御
1 ばね定数を調整する方式(自己最適化ダンパ)
2 粘性係数cを調整する方式
3 質量を調整する方式(衝撃応答抑制機能を有するセミ・アクティブダンパ)
4 予見動作機構を有するセミ・アクティブダンパ
第4章 能動方式による振動制御
1 アクティブコントロールの基本原理
2 モード制御
第5章 振動制御適用例
1 サーボダンパによる振動制御
2 自励振動の抑制
3 空気ばね支持方式による能動振動絶縁
4 剛性支持方式による能動振動絶縁
5 衝撃振動の抑制
第二部 分布定数系の振動制御
第6章 柔軟はりの振動制御
1 柔軟はりの記述
2 伝達マトリックス法によるはりの解析
3 フィードバック制御系の記述
4 DVFBとコロケーション
第7章 Active Boundary Control(ABC)法
1 ABC法の原理
2 境界条件の生成
3 ABC法と振動制御
第8章 平板の振動制御
1 固有値問題
2 平板の振動方程式
3 単純支持平板
4 平板の振動制御
第9章 スマートモード制御
1 三次元スマートセンサ
2 三次元スマートアクチュエータ
3 二次元スマートセンサ
4 二次元スマートアクチュエータ
5 単純支持平板のスマートモードセンシング
6 単純支持平板のスマートモードアクチュエーション
第10章 平板のポイントモード制御
1 ポイントセンサを用いた一般モードフィルタリング
2 分布センサを規範とするポイントセンサによるモードフィルタリング
3 分布センサを規範とするポイントアクチュエータによるモードアクチュエーション
4 モード制御
第11章クラスタ制御
1 一つの情報量を制御する場合
2 全ての情報量を制御する場合
3 矩形平板のクラスタ制御
4 柔軟はりのクラスタ制御
第12章 パワーフロー制御
1 パワーフロー
2 振動インテンシティのフローパターン
3 渦巻きタイプの生成メカニズム
4 渦巻き型パワーフローの生成
参考文献
索 引
説明
戦後奇蹟の復興を遂げた日本経済社会は、その副産物として公害をも排出した。今で言う環境破壊である。70年代当時は、典型7公害と呼ばれた。中でも振動騒音に関する苦情件数は、全体の1/4を占め、その数字は現在でもほとんど変わりがない。当時、公害を抑制する技術開発に先んじて、騒音規制法や振動規制法が施行されてしまった結果、高度成長を支えてきた町工場は、操業を停止せざるを得ない状況に追い込まれた。法で施行された数値をクリアできないからである。最も深刻な打撃を被ったのは鍛造工場である。鍛造工業は、産業の基幹を支える必須の存在であるが、その加工自体が、物を叩いて作業する性質上、音や振動は機械自体の持つ致命欠陥と言われた。町工場ではこのような鍛造機械やパンチプレスを大黒柱に、営々と物造りに励んでいたが、かかる法規制により操業もままならなくなり、周囲住民からの苦情が起きる度に、人里離れた土地を求めて工場を移転させざるを得ない状況に置かれた。小生の知るかぎりでは、4度移転した鍛造工場がある。当時、公害ジプシーなどと揶揄された。4度目に選んだ移転先は、苦情など絶対に起こりえない山中であった。このように、当時から現在に至るまで、技術の担い手は絶えず移転を余儀なくされる。さて、山中に工場を構えた操業者は、やっと安住の地を得たかといえば実はそうではなく、今度は騒音振動が原因で、野鳥が卵を産まなくなってしまったとか、生態系がこわされるとの理由で、終には野鳥にまで追い出しを喰わされてしまったのである。悲惨である。その当時から、技術の担い手は非情さを知っている。適切な低振動化、低騒音化の技術開発が進んでいれば、このような悲惨さは回避し得たのだが、静粛化技術の未熟な時代の悲劇である。
本書は小生がこれまで辿ってきた振動制御工学を総括し、いわば独善的に記述した傾向は否定できない。振動制御は実学である。現場で役立つ知見を必要とする。きれい事ではない。小生が大学院博士課程の学生であった頃、制御を具体的に適用することなど未だ珍しかった時代に、研究室の片隅でサーボダンパの実験を繰り返していた。今で言うアクティブダンパである。油圧サーボ機構で駆動されるサーボダンパによりフィードバックする作業では、変位フィードバック、速度フィードバックなどを総動員して試行錯誤を繰り返しながら制御効果を追っていく。ちょうどその頃、運良く、ある工作機械メーカーより相談が持ちかけられた。大型門型立て旋盤においてびびり現象が発生して困っているというのである。そこで早速、現場に乗り込んでその振動を抑制することにチャレンジしたのである。若気の至りであったのかも知れない。ちょうどダビデがゴリアテに挑むような心境であった。現場に到着してみるとしばし唖然。そこで対峙した工作機械の巨大さに唯々たじろぐばかりであった。テーブル直径が4メートル、一抱えもある巨大なラム(ボーリングバー)の突出し長さが2メートル。しかも作業環境がすこぶる悪いのである。これまで薄汚れたものとして感じ取っていた研究室など、いわば純粋培養とも言える理想に近い環境であった。現場は騒音と振動に満ちており、頭上には大型クレーンが地響きを立て走行し、また近くでは搬送用ビークルが絶えず騒音と振動をまき散らしていた。フィードバック信号を採取すべく、ラム先端に設置した加速度ピックが無用の長物に感じたのはその時であった。加速度計は絶対加速度を採取するので、建屋を含めた構造全体の振動現象をセンシングしてしまう。サーボダンパを駆動するに必要なフィードバック信号をどうとるか?ラム自身の振動などとても検出できるような状況ではなかったのである。そこで急遽作戦変更して、万が一にそなえ用意した歪みゲージをラム表面に貼付した。加速度計は使い物にならない。すなわち、絶対変位から相対変位測定への変更である。それでもノイズレベルは半端なものではなく、研究室で扱っていた波形とは大きく異なっていた。不要なノイズを除去するにはフィルタをかませなければならないが、その結果位相まで変化してしまい、まともにフィードバックなどかからなくなってしまう。それでもなんとか、試行錯誤を繰り返しつつ、ようやくフィードバックがかかりサーボダンパを駆動させると、これまでゴツゴツと唸り音を出して毟り切削していた状況が激変し、シュルシュルと流れ型の切り子が発生し、びびり振動が止まったのである。周りで見物していた技術者からの万雷の拍手があがった。その瞬間の満足感は今でも忘れることのできない私の宝物である。

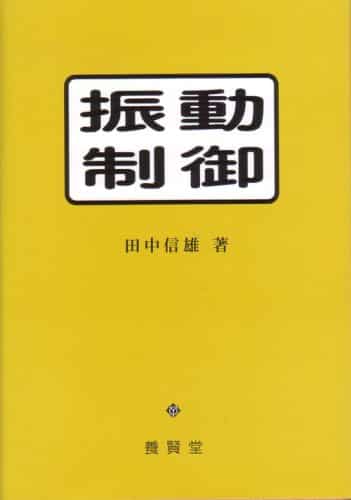
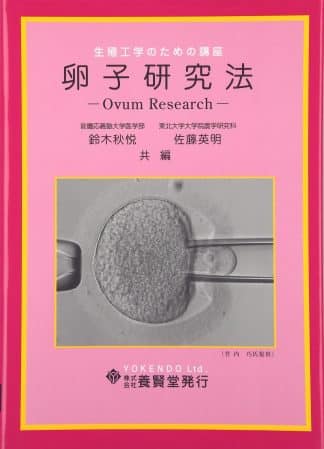

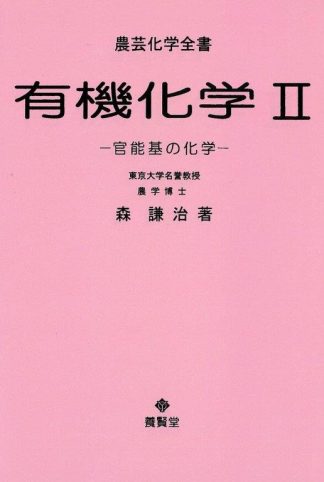










レビュー
レビューはまだありません。