目次
第1章 モノづくり技術の発展の流れ
1.1 モノづくりとは
1.2 モノづくりパラダイムの変遷
第2章 モノづくりにおける評価基準
2.1 モノづくりにおける評価項目と評価基準
(1.品質・性能:2.製造コスト:3.納期・リードタイム・需要・在庫:4.生産の方式に関わるもの:5.生産におけるフレキシビリティ:6.工程能力:7.安全性・信頼性:8.環境・資源:9.精神的満足度)
2.2 評価基準に対する要求
2.3 評価基準と最適化との関連
第3章 モノづくり革新のための技術
3.1 より広い可能性からより良いモノの創成
3.2 概念からの創成
3.3 コンカレントエンジニアリング
3.4 コラボレーション
第4章 モノづくりにおける人間の関わり
4.1 モノづくりにおける人間の役割49
(1.人間の能力:2.顧客と生産者との関係)
4.2 感性工学
4.3 人間工学
4.4 コラボレーション環境
第5章 モノづくり支援技術
5.1 各種支援技術
(1.製品形状認識技術:2.性能特性解析技術:3.発想支援技術:4.データベース技術:5.製造支援技術:6.顧客ニーズ獲得技術:7.企業経営支援技術)
5.2 モノづくりへの情報システムの活用
第6章 モノづくりのための最適化技術
6.1 最適化の背景と最適化を困難にする点
6.2 最適化の基本戦略
6.3 システム最適化
(1.タスクの実施や評価特性最適化の順序決定問題:2.2段階統合的最適化:3.特性分解と単純化に基づく階層的多目的最適化法:4.代替設計案の最適選択法)
第7章 意思決定法
7.1 意思決定を困難にする点と容易にするための基本方策
(1.意思決定を困難にする点:2 意思決定を容易にするための基本的方策)
7.2 意思決定の基礎
(1.多くの評価項目のもとで最良の代替案を選択する方法:2.一対比較法による属性に対する重みの計算:3.AHP法による代替案の決定法:4.不確定な状況での主観確率を用いる意思決定:5.意思決定者の選好基準を考慮した意思決定)
7.3 コラボレーション環境での意思決定のための方策
第8章 モノづくりによる文化の形成
索引
説明
本書は、モノづくりのための技術という非常に広い範囲の分野を“最適化”の立場からまとめたものである。 モノづくりは、経済力の維持、国民の生活レベルの向上と直接的に関連し、われわれ人間にとって最も根幹的なことである。そのモノづくりは、この100年余りの間に大きく発展し、大きく様変わりしてきた。モノづくりにおける製品機能、性能、品質、製造コストなどの面での熾烈な競争ばかりでなく、現在では、安全性、環境への配慮、資源のリサイクル、部品のリユース、感性面での顧客の満足度など、多くの要因を考慮したうえで、製品の開発・設計を実施しなければならない状況にある。この状況では、より望ましいモノづくりの実現は、これまで以上に複雑で困難な意思決定の連続である。このような背景のもと、従来の個々の領域での改善や最適化ではなく、関連する多くの事項を考慮したうえで、より望ましいモノづくりのための意思決定をできるだけ論理的な根拠のもとで、より迅速に実施する技術、いわば最適システム技術の活用が重要な時代を迎えている。
最適化という概念や方法は、数学的な記述や捉え方がなされることが多いが、工学での研究、産業界で業務や仕事に活用するうえでは、数学的に厳密なことはさほど重要ではなく、基本的な考え方や手法、意思決定の対象となる問題の捉え方などに重要な意味をもっているように思われる。しかし、“最適”という用語は、しばしば、対象とするものが従来より好ましいものであるというときや、より望ましいものを選択する状況で、気軽に曖昧な意味で使われることが多い。そのような折にも最適化の基本的な考えや意味づけがなされれば、もっと説得力があり、発展しうる議論がなされると考える。社会で活躍している著者の研究室の卒業生が、研究室で学んだような最適化の考え、センスが日常の仕事の中で非常に役立っているということをしばしば耳にする。そこでは、最適化のツールが役に立つのでなく、考え方、センス、概念、思想が役にたち、それを知らない人との差別化がなされるといっている。
最初にも述べた状況から、これからのモノづくりにおいては、より望ましい新しいものを創成すると同時に、多くの要因を考慮したうえでの最良の調和を追い続けることが必要である、それらを実現するうえで、“最適化”という概念と技術が必要である。また、モノづくりに関連する技術は、新しいものが次々と生まれるが、その本質を“最適化”という技術でまとめることにより、ある方向性が見えてくる可能性もある。本書では、そのことに関連するような重要なモノづくりの技術はできるだけ含めるように努めた。
まず第1章で、この100年余りの間に劇的に変貌したモノづくりのパラダイム(考え方の枠組み)の変遷を述べる。この考察は、これらかのモノづくりの方向性を考えるうえでも重要な意味をもつと考える。より望ましいモノづくりを実現するための考え、方法論、技術を議論するのが本書の目的であるが、第2章では、その目的を実現するうえで関係するモノづくりにおける基本的な技術と、より望ましいと判断するための評価基準を説明する。そして、評価技術と最適化との関連を議論する。第3章では、そのより望ましいものを実現するには、モノづくりの過程における根本、概念、コンセプトからの革新が必要であるとして、より望ましいモノづくりのための基本概念を述べる。その革新においては、人間の役割が重要であり、第4章では、モノづくりにおける人間の関わりについて説明する。そして、第5章では、それを実現し実行するには、モノづくりに関連する意思決定を行う人間を有効に支援するシステムが必要であり、それらの種々のシステムを分類して説明する。またその支援のうえで、情報システムの働きを説明する。それらの支援システムを用いて、モノづくりにおける最良の意思決定を行うには、まず最適化技術が必要である。第6章では、モノづくりにおける最適化技術の現状と基本を説明し、最適化の基本戦略、システム最適化の技術を議論する。より望ましいモノづくりを実現するうえでの支援技術の目的は、対象とするモノづくりの問題に対して、より望ましい意思決定結果を得ることである。第7章では、その意思決定の基本的な手法と考え方を説明する。最後に第8章では、まとめとして、モノづくりの目的である産業の活性化とより高次元な目的である文化の形成との関係を述べる。
(序文より)

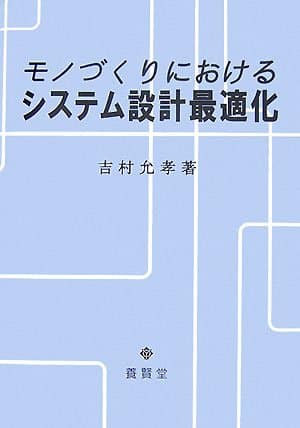


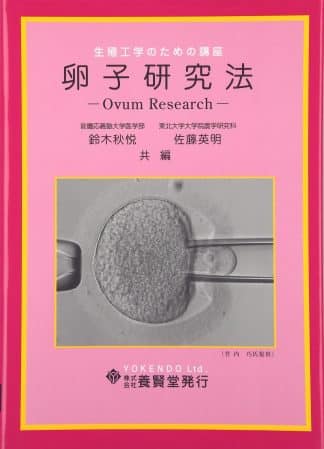










レビュー
レビューはまだありません。