目次
産業動物
日本の畜産と農業のレビュー
~その12 戦後75年の飼料に関する25のキーワード~
畜産飼料調査所主宰
阿部 亮
国際競争力を付けるための肉用牛の効率的生産手法
元ナンチクファーム代表取締役
北野良夫
飼料学(191)
―海獣、魚の飼料―
静岡県立農林環境専門職大学
祐森誠司
(一社)日本科学飼料協会
石橋 晃
家畜飼養管理の実践(14)
―家禽の管理―
静岡県立農林環境専門職大学生産環境経営学部
祐森誠司
元東京農業大学
佐藤光夫
静岡県畜産技術研究所中小家畜研究センター
柴田昌利
生物統計学講座(9)
―定性値・頻度データ(χ2およびFisherの検定)―
元慶応義塾大学総合政策学部非常勤講師
小林克己
第113回日本養豚学会大会開催報告
日本養豚学会会長・静岡農林環境専門職大学生産環境経営学部
祐森誠司
日本養豚学会常務理事・農研機構畜産研究部門
佐々木啓介
日本養豚学会副会長・農研機構生物機能利用研究部門
美川 智
Dr. Ossyの畜産・知ったかぶり(116)
戦争と動物①ウマ
麻布大学名誉教授
押田敏雄
静岡県立農林環境専門職大学生産環境経営学部
祐森誠司
長崎のウシの去勢術
広島大学大学院生物圏科学研究科・長崎県肉用牛改良センター
松尾雄二
コロナ禍等に伴う食糧危機・これからの農牧生産・食糧増産戦略の必要性(2)
―コロナ禍に伴う食糧危機に対する二案―
(株)宏大 & エクアドル、リトラル工科大学
冨田健太郎

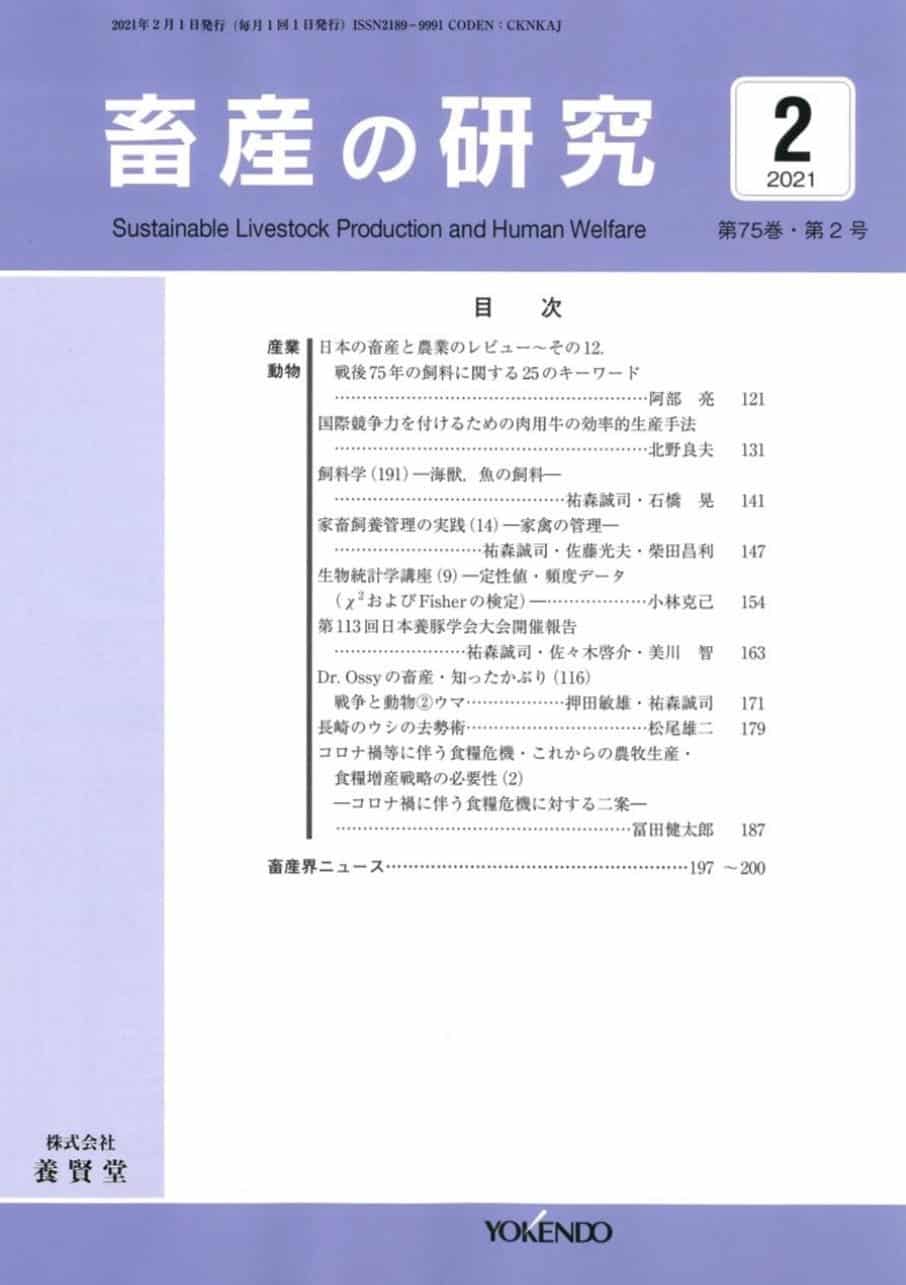
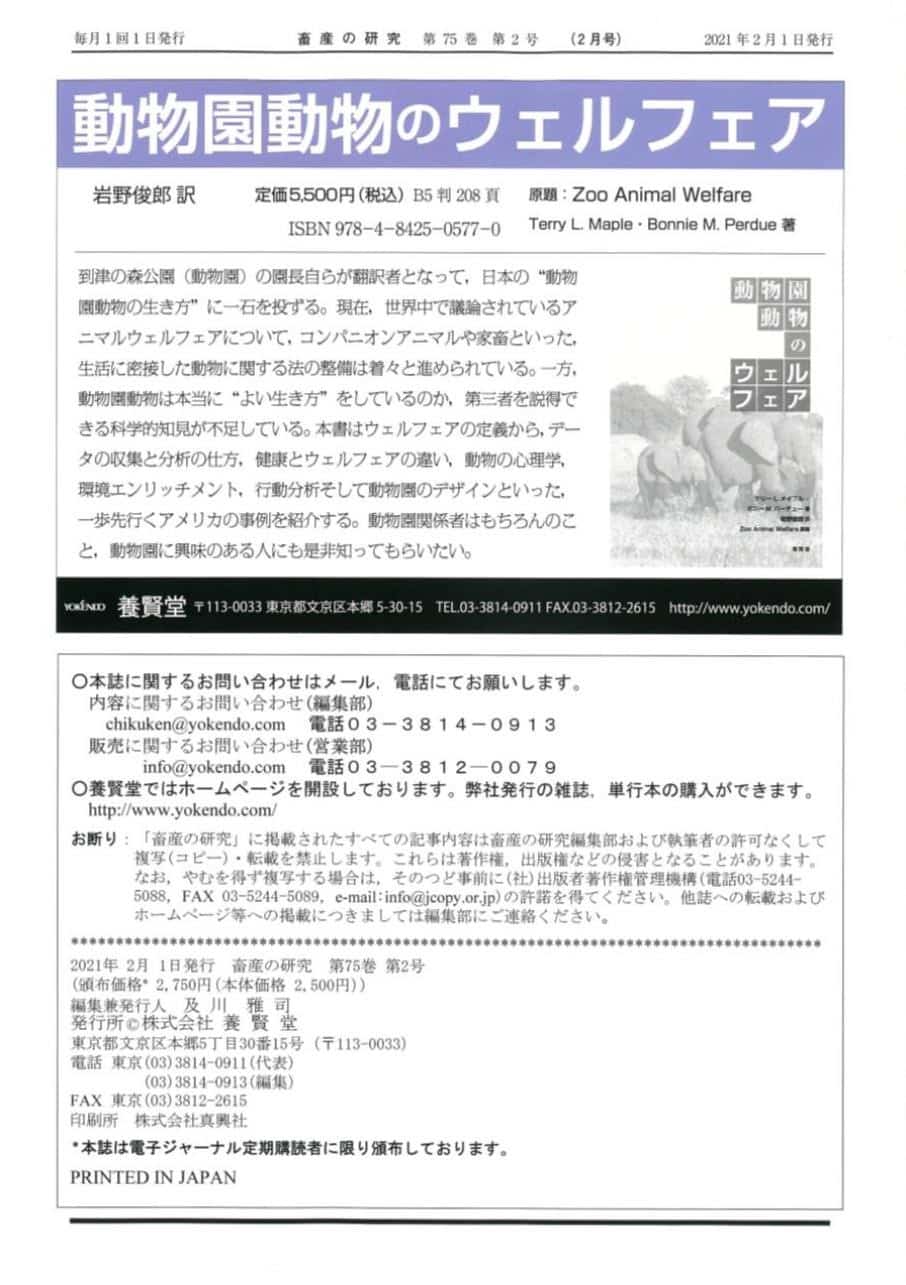















レビュー
レビューはまだありません。