目次
まえがき
第1章 光合成産物の転流と分配の基礎的知識
1.光合成産物の転流・分配研究の基礎技術
2.11CO2を用いた最新の光合成産物転流・分配の測定法
3.光合成産物の再転流および貯蔵器官からの再転流
4.転流物質・貯蔵物質の形態
第2章 葉序および葉序に伴う維管束走行と光合成産物の転流・分配
1.トマトの葉序と維管束配列・走行
2.栄養生長期における葉位別・生育ステージ別の分配パターン
3.果実肥大期の維管束走行とそれに伴うソース・シンク関係
4.花房直上葉と直下葉の光合成産物の転流・分配と花房発育ステージ
第3章 環境要因と光合成産物の転流と分配
1.温度と光合成産物の転流・分配
2.光環境と光合成産物の転流・分配
3.水分状態と光合成産物の転流・分配
第4章 植物ホルモンと光合成産物の転流と分配
1.トマトトーン(4-CPA)がトマトの果実肥大に及ぼす影響
2.ベンジル・アデニンがキュウリ果実の肥大に及ぼす影響
第5章 光合成産物の転流・分配における葉の役割と栽培ステージの影響
1.トマトの葉のステージ別光合成能と摘心処理が転流・分配に及ぼす影響
2.果実肥大期における葉位別分配パターンの変化
3.花房内の果実間分配と種々の花房のソース・シンク関係と葉位
4.ソースとシンク葉の摘除と暗黒化処理がトマト苗のソース・シンク関係の変化に及ぼす影響
5.トマトにおける葉の物質生産性とソース・シンク関係の経時的変化
6.トマトにおける各葉の物質生産性と果実肥大に対する葉の寄与度
7.キュウリの維管束走向と葉位別転流・分配
8.イチゴの栄養生長期から休眠期にかけての光合成と光合成産物の転流・分配
9.イチゴ果実の発育と光合成産物の転流・分配
第6章 光合成産物の転流・分配における収支
1.光合成産物の炭素収支の定量解析の意義とその経時的変化
2.光合成産物の転流・分配および呼吸と炭素収支バランスに及ぼす夜温の影響
3.光合成・蒸散・呼吸および光合成産物の転流・分配に及ぼす培地温の影響
4.光合成産物の葉位別炭素収支とその総合的解析
5.日照時間の変更による光合成量の変化がトマトの光合成産物の転流・分配および炭素収支に及ぼす影響
6.異なる光環境下で生育した苗における光強度の変化がトマトの光合成産物の転流・分配および炭素収支に及ぼす影響
7.キュウリ苗の光合成産物の転流・分配および炭素収支に及ぼす温度と光強度の影響
説明
野菜の栽培に限らず,作物の栽培をするにあたっては,収量を高めることが主な目標となっている.収量は種々の栽培環境と種々の生理作用の結果として現れてくるものであるが,その中で,生産量の原資である光合成作用と光合成産物の転流・分配が重要である.
野菜,特に果菜類においては,果実の生産と新葉の伸長と花芽の分化といった,いわゆる,栄養生長と生殖生長とが同時に多層多段階に繰り広げられており,ソースとシンクの関係も単純でなく,各生育段階においては,果実の摘除・収穫,葉の摘葉・整枝というような栽培操作によるシンクやソース関係の変化に対応した作物側からの反応があり,種々の栽培操作や生育段階における光合成と光合成産物の転流・分配の変化がその作物の収量,すなわち生産性に大きく影響を及ぼしていることが考えられる.
このことは,野菜栽培では,光合成量が生産量に大きな影響を与えるが,光合成量と生産量との関係は,単純な系で説明できるものではなく栽培環境や栽培法によっては必ずしも最大の収量と効率的生産になっていない場合もあることに留意する必要がある.
したがって光合成産物の動態,すなわち光合成された同化産物がどのように動き,どのように分配されるかを知ることが重要になってくる.野菜における生産性の維持は光合成産物が果実だけに分配されるだけでよいのか,将来果実になる充実した花芽の分化や将来の果実生産を担う新たな葉の生産をどのように維持するのか,それらの生産をどの葉が担うのか等々,多くの課題を解析することが栄養生長と生殖生長を周期的に次々と繰り返す野菜の生産性を解析する鍵になると考えられる.
近年では,野菜の生産性を高めることの重要性が認識され,そのため,植物工場などの野菜生産において,環境制御技術の高度化が行われてきている.これらの技術開発は全て野菜の生産性を高めることを目的にしたものである.放射性同位元素である14C を用いた実験手法は光合成産物の転流 ・ 分配を確実に解析できる優れた方法であるが,放射性物質の取り扱い上の制約,高額な必要機器や RI 施設の設置等の制約があり,著者らの研究終了後は,国内外で生産性の基である光合成産物の転流・分配に関する研究はほとんど行われていない状態が続いてきている.特に,実際栽培における種々の状況に対応した光合成量の変化,光合成産物の動態を明らかにしようとする研究が少なくなっている.
そこで,著者等が光合成産物の転流および分配を実際栽培の条件に出来るだけ対応した形を作り出して得られたデータを中心に述べ,さらにその中から転流・分配の作用機作にかかわる部分についても解析を試みた.それらは必ずしも,すべてのケースを解析し尽くしたとは言えないが,ある程度目安となる知見を集積したデータで示し,実験項目ごとに得られたデータの意味するところを考察したものである.こうして得られた知見は,栽培現場にかかわる普及員・研究者の実際栽培を支える技術の基礎として利活用されることを期待し,さらに残る問題点等を浮き彫りにし,今後の研究を支える若い研究者 ・ 学生諸氏の新たな研究の進展および栽培技術の進展の一助になることを願い,本書を上梓した.

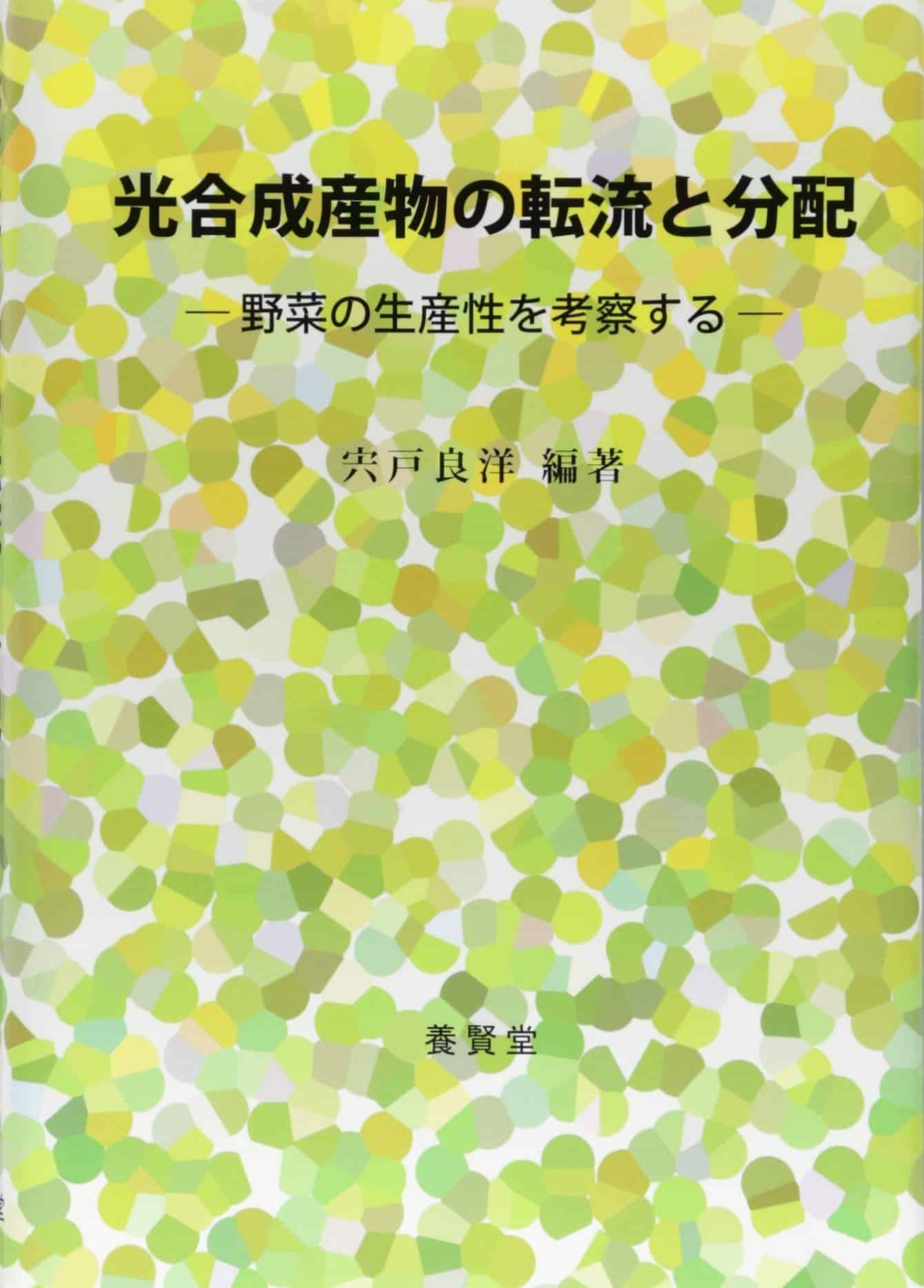
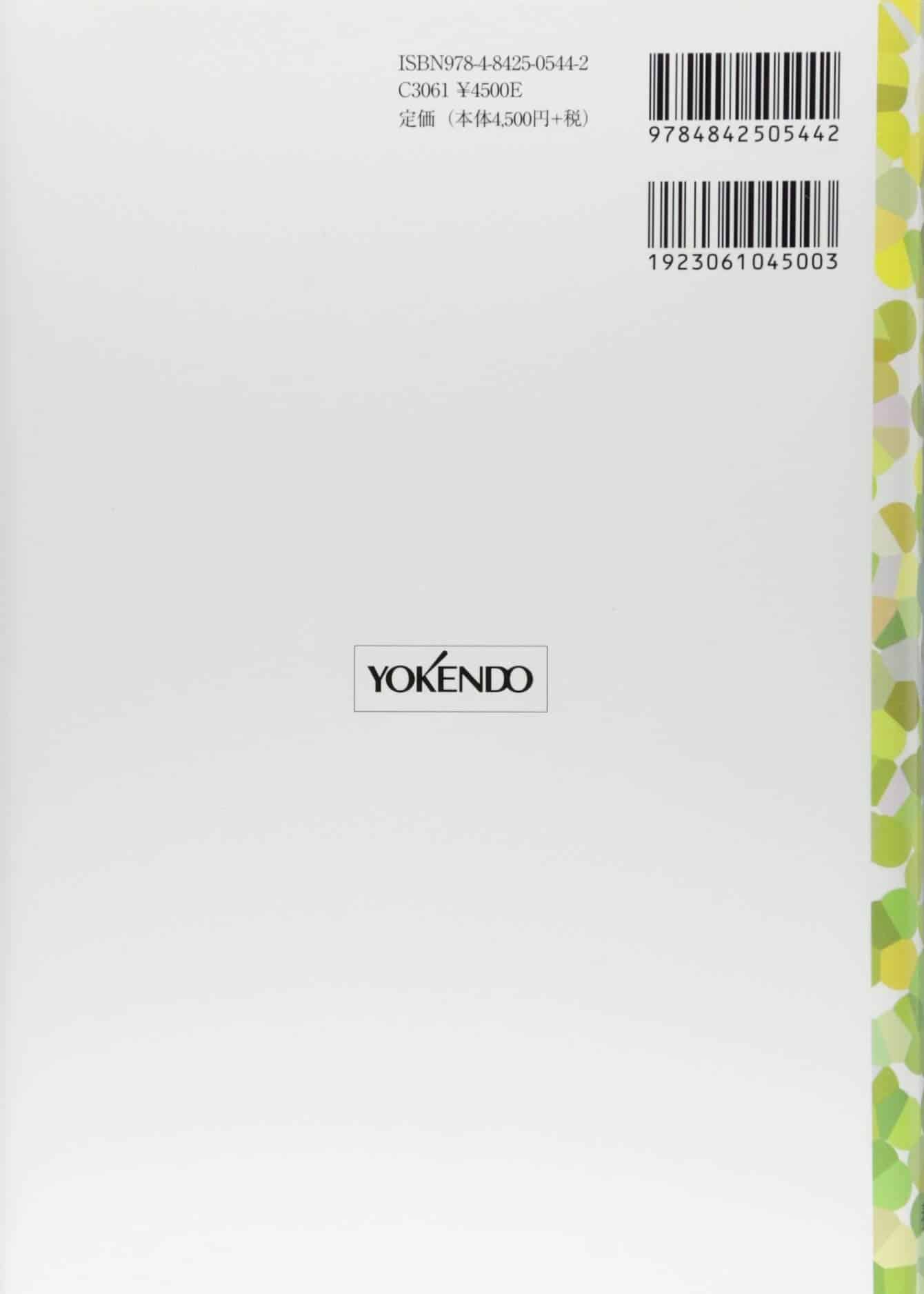

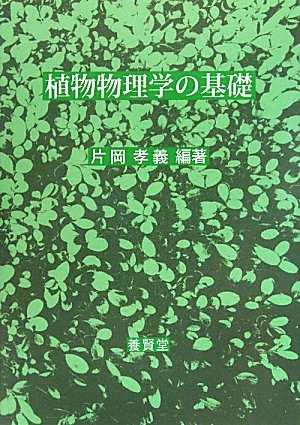
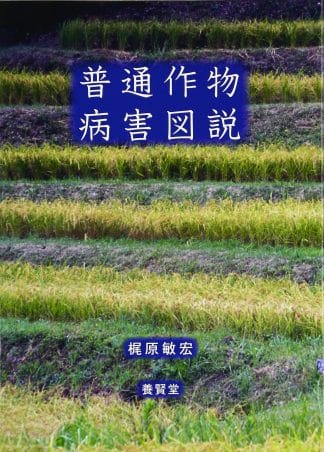











レビュー
レビューはまだありません。