目次
まえがき
(解題)農業・農村のエンタテインメント・デザインを考える
1.農作業・農業体験と教育的効果
農業体験学習の教育的効果に関する実証分析
三世代協働畑体験の教育的意味と効果
農業・農村体験の教育・保健休養効果についての心理的・生理的評価
農業者による農業体験活動の展開と発展要因-福井県若狭町かみなか農楽舎を事例として-
農村における博学連携地域学習の教育的効果と可能性
2.伝承文化が守る農業と農村生活
文学から見た農村-詩人たちは農村に何を見てきたのか-
サクラと農業
『遊び仕事』としての農-前栽畑と市民農園の類似性-
昭和戦前期における青年の「暮らし」からみた「地域づくり」-群馬県旧勢多郡北橘村上箱田集落を事例として-
3.ランドスケープとしての農村を守る
農村ランドスケープの構造と変化-自然と人間の相互作用の移り変わり-
歴史的な農村景観の形成過程と評価-棚田景観の変容と認知・評価構造-
農村の色,地域の色の見方,考え方
農村と都市におけるサウンドスケープの定量的評価
4.生き物に優しい農村を育てる
農業・農村が守ってきた生物の生息環境
農業に依存してきた農村の植物
里山環境の歴史性を追う
農業排水路の環境配慮手法からみた底生生物相と安定同位体比
5.農家と消費者をつなぐ情報コミュニティ
CSAによる生産者と消費者の連携-スイスと日本の産消連携活動の比較から-
情報システムによる都市と農村のコミュニケーション
6.住民参加ワークショップによる農村づくり
ワークショップで地域資源の活用を学ぶ
体感ワークショップから始まる農村環境づくり
ムラとムラを結ぶワークショップ-集落が限界化するまえに-
「ふるさと」を掲げる農村づくり再考
あとがき
説明
新緑が芽吹いた里山には水が入り始めた水田が広がり、小川に生き物の気配を感じながら、集落に鯉のぼりや吹き流しを眺める。そのような農村の風景には誰もが安らぎを感じる。
このような空間は、先人達が長い年月をかけて農地を拓き水を引いて農業生産の場とし、安全な場所に生活の場を築き、そこに文化を醸成してきたことで創り出された。管理された農地や農業水利システムは、国民食料の安定供給の基盤として、また国土保全機能や生物多様性保全機能等の公益的機能を発揮する場として、さらに農村の営みが育む美しい景観や伝承文化は人の心を豊かに、優しくする資源として、いずれもなくてはならない国民共有の資産となっている。
かつて日本学術会議が農業の多面的機能を検討した際、国土保全機能のように代替法などで経済評価を行ったが、農業にはそれらよりもはるかに膨大な機能があるとした。とくに、その資産的価値が計りにくい要素は、人格形成に及ぼす効果である。農村を体験し、あるいは深く関心を持つことで、水や土の大切さ、生命の大切さ、人と人の絆の意義と自らが果たすべき責任を正しく理解できる資質が育まれる。自然環境の持つ容量や循環の原理を逸脱したことで滅んでいった文明の歴史に理解がつながり、経済社会のグローバル化の中で、水資源の濫用や生態系の破壊、地球温暖化や食料不足等が進行する現状とその問題点を正しく捉える力につながるに違いない。古い時代から校歌には必ずと言っていいほど地域の山川などの自然が謳い込まれている。それは立地を表すに止まらず、人を育む環境を謳ったものと理解される。
農村工学研究所は、今、農村振興施策を科学技術面から支援するため、農地・水資源や農業水利施設等ハード面に係る研究と、農村景観や多様な生物、そして地域の社会機能とそれを支える伝承文化等の農村資源を守り活かすソフト面の研究を推進している。
本誌は、養賢堂発行の「農業および園芸」誌、第83巻第1号(2008年)上で特集された内容をベースに、加筆・再編し、農村のソフト面に係る研究活動を紹介したものである。緒についたばかりの研究もあるが、農村工学研究所が工学、環境科学と人文・社会科学の分野の総合化により農村研究に取り組んでいる姿を理解いただければ幸いである。

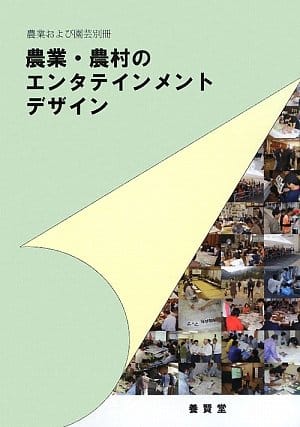

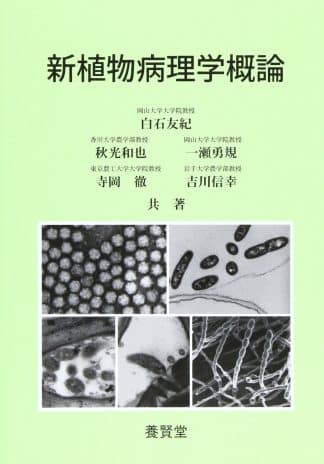
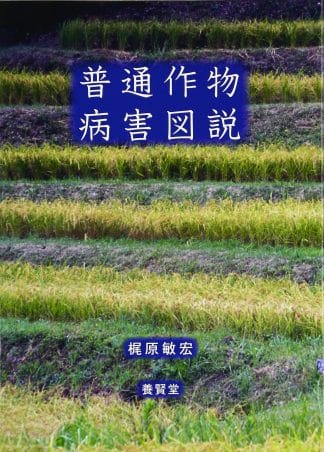

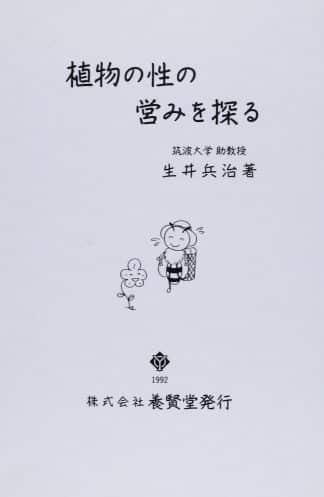










レビュー
レビューはまだありません。