目次
序章
第1章 一代雑種の品種はどんな作物で使われているか
第1節 野菜類の一代雑種-その多様性-
1.トマト
2.キャベツの仲間
3.ハクサイ
4.タマネギ
5.ホウレンソウ
6.キュウリ
7.ニンジン
第2節 一代雑種のモデルとしてのトウモロコシ
[その1:背景にあるもの]
1.トウモロコシはインディオの宝
2.移住民とトウモロコシ
3.極東の日本では
第3節 一代雑種のモデルとしてのトウモロコシ
[その2:50年間で単収倍増]
1.はじめは疑心暗鬼
2.F1の優秀性を支えているもの
3.10年で10ブッシェル/エーカーずつ増収
4.アメリカに追いつき追い越せ
第4節 予想外の一代雑種利用-ヒマワリからイネまで-
1.ヒマワリ
2.テンサイ
3.ソルガム
4.ナタネ
5.コムギ
6.イネ
第5節 13億人を養うハイブリッド・イネ
1.イネのハイブリッド化での課題
2.細胞質雄性不稔性の存在
3.ハイブリッドでは可稔となること
4.ハイブリッド種子生産上の隘路とその便法
5.ハイブリッド・イネの多収性
6.ハイブリッド・イネの現状
第2章 一代雑種の遺伝学-ヘテロシスの科学-
第1節 近代遺伝学の申し子としての一代雑種
1.メンデルの法則の再発見
2.雑種強勢の発見
3.ヘテロシス研究のあけぼの
第2節 終わりなきヘテロシス理論の論争
1.ヘテロ接合であることの意味
2.ヘテロシスはまず胚に現われる
3.生長量・生長率に現われるヘテロシス
4.酵素活性に現われるヘテロシス
5.雑種酵素とは
6.生長物質がヘテロシスを制御する
7.計量遺伝学の示すもの
8.ミトコンドリアでの相補性
9.半数体なのにヘテロシスが現われる
10.ゲノム研究の周辺から
第3節 トライアル・アンド・エラーの実際
1.八方美人でまず選抜
2.抵抗性を組合わせるハイブリッドの場合
第4節 雑種こそ生物集団のあるべき姿
1.種の進化の中でヘテロシスをどう見るか
2.ヘテロ接合が優勢であること
3.個体のヘテロ接合性と集団を構成する個体のヘテロ性
第3章 一代雑種種子の採種技術とその科学
第1節 子孫繁栄のための植物の繁殖戦略
1.他殖こそ植物の本性
2.他殖の機作
3.他殖であることの長所と短所
第2節 完全な交雑種子を生産する
1.雌雄異株と雌雄異花の場合
2.不和合性遺伝子の功績
3.完全なヘテロ接合を保証する雄性不稔性
第3節 ダメ雄となる遺伝子の有用性
1.核雄性不稔遺伝子の制御の方法
2.核=細胞質雄性不稔遺伝子の科学
3.バイオテクノロジーの世界
第4節 交雑しないで一代雑種の種子を作る
1.アポミクシスの種類
2.アポミクシスの系統を作出する
3.アポミクシス・ハイブリッド種子を作る
4.イン・ビトロで種子を増やす
第4章 新しいテクノロジーとの接点
1.バイオテクノロジーの様相
2.バイオテクノロジーとハイブリッド育種
索 引

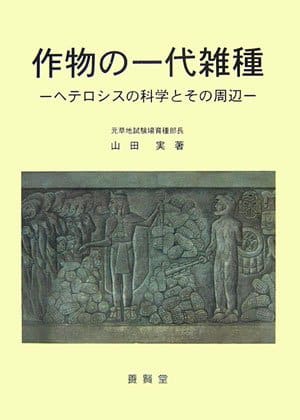













レビュー
レビューはまだありません。