目次
第1章 2次元問題における応力集中
1.円孔による応力集中/2.だ円孔による応力集中/3.有限幅の板の中の円孔による応力集中/4.等価だ円の概念/5.介在物による応力集中/問題:文献
第2章 き裂による応力集中
1.き裂先端近傍の応力の特異性/2.二軸応力場のき裂近傍の応力分布/3.き裂先端近傍のせん断応力分布/4.短いき裂と長いき裂/5.き裂先端の塑性域/6.K1の概算法/7.き裂の伝ぱ経路/問題:文献
第3章 3次元問題における応力集中
1.球状空洞(球か)における応力集中/2.球状介在物による応力集中/3.回転だ円体状介在物による応力集中/4.ピットによる応力集中/5.3次元き裂による応力集中/問題:文献
第4章 応力集中の干渉効果
1.応力集中が増加する干渉効果/2.応力集中が減少する干渉効果/3.ボルトのねじの応力集中/問題:文献
第5章 疲労における切欠き効果と寸法効果
応力集中からの視点/問題:文献
第6章 板曲げにおける応力集中
1.円孔を有する広い板の曲げにおける応力集中/2.だ円孔を有する広い板の曲げにおける応力集中/問題:文献
第7章 有限要素法(FEM)の使い方
1.要素分割の基本/2.弾塑性解析/3.き裂や非常に鋭い切欠きの要素分割/問題:文献
第8章 内圧または外圧を受ける円筒と切欠き
1.基本解/2.内圧を受ける円筒の内壁のき裂/3.焼きばめの問題/4.その他の問題/問題:文献
第9章 集中荷重を受ける円板
1.基本問題/2.円板の中の円孔/3.種々の集中荷重/問題:文献
第10章 集中力による応力集中
1.半無限板の縁に作用する集中力/2.無限板中に作用する集中力/3.円孔の縁に作用する集中力/4.解の応用/5.半無限体の表面に垂直に作用する集中力/文献
第11章 熱応力による応力集中
1.2次元円形介在物のまわりの熱残留応力分布/2.熱衝撃による応力集中/3.球状介在物のまわりの熱残留応力/文献
第12章 転位による応力集中
1.基礎式/2.すべり帯による応力集中/文献
第13章 接触応力による応力集中
1.接触応力場の基本的性質/2.2次元剛体パンチによる応力集中/3.円形剛体パンチに押込みによる応力集中/4.二つの弾性体の接触による応力集中/文献
第14章 ひずみ集中
文献
付録
1.弾性力学の基本/2.き裂先端の応力場/3.円孔またはだ円孔の寸法が板幅に限りなく近づいた極限での応力集中係数/4.板の中のだ円孔による応力集中と応力分布/5.外周に周期的な集中荷重を受ける円板の中心の応力/文献
問題の回答とヒント索引
説明
本書は著者が長年暖めてきた応力集中に関する考え方を簡潔にまとめたものである。応力集中のデータを集めたハンドブックではなく、基本的考え方を示したものである。応力集中に関する基本的な事項、典型的な間違いやすい概念、応力集中問題に対する新しい考え方について説明している。執筆の動機は近年の日本の製造業のもの作りにおける基本力の低下を痛感したことにある。破壊事故がもたらす経済的損失はGDPの約4%に達するという調査結果が米国とヨーロッパで示されている。
科学や技術が進歩しても破壊事故は後を絶たない。むしろ、巨大事故は頻発している感がある。大学や企業で長年材料力学や弾性力学に関する講義を続けてきて、近年特に感じることは、弾性力学の基本的知識が身についていない技術者が増えていることである。
弾性力学の教育はとかく数学的になりがちである。多くのテキストの内容の構成がそのことを物語っている。そのようなテキストは研究者には役立つかもしれないが、ほとんどの技術者には全くといっていいほど利用価値がない。著者は、かなり以前からそのことに気づき、弾性力学の教育方針を根本から変えて、多くの学生、技術者に役立つ考え方を示してきたつもりである。強度設計技術者や品質保証技術者に特に要求されることは、弾性力学の基礎知識をしっかり身につけることと、それをもとに「応力集中の考え方」のセンスを身につけることである。その内容はそれほど難しいことではない。むしろ、問題に親しむにつれ、応力集中の問題は楽しいパズルのような考え方に満ちていることが理解できるであろう。
事故は精密な応力解析の失敗によって起こるのではない。最近は、有限要素法ソフトウエアで解析したから大丈夫という安易な姿勢が見られる傾向がある。この種の安易な考え方は、単にマニュアルや設計書の指針が示す許容値を満足すればよいという姿勢からくる。このようなところに、コストダウンの号令によって技術の空洞化が生じた日本の製造業の欠陥が見えてくるのである。
疲労破壊に代表される事故の原因となる破壊はほとんどの場合、応力集中部が起点となる。機械や構造物は色々な形状をしているので、機能的な面から応力集中は避けることができない。したがって、設計者は応力集中が過大とならないように形状を工夫したり、応力集中を正しく評価することが必要である。
本書では、主として、弾性応力集中を扱う。弾性状態でのひずみは、フックの法則を使って応力との関係から求めることができる。弾塑性状態になれば、応力とひずみの関係はフックの法則から逸脱し、応力の集中とひずみの集中をフックの法則では関係づけることができない。切欠き底で降状が起こると、応力集中係数は弾性状態の値より低下するが、ひずみ集中係数は弾性状態の値に比べて著しく上昇する。したがって、弾塑性状態ではひずみの集中に注目して疲労強度を論じることになる。しかしながら、切欠き底において降伏後もフックの法則からの逸脱が少ない場合や降伏後に材料の加工硬化が起こる場合には、弾性応力集中に注目して疲労強度を論じてもよい。一般に、高サイクル疲労強度を議論する場合には弾性応力集中係数に注目するのが現象にそった考え方でもあり、実際の解決にも適切かつ有効である。したがって、弾性状態の応力集中の性質を理解することが最も重要なのである。
本書によって、応力集中の考え方のセンスを身につけ、必要に応じてFEMなどの解析ソフトなどで補って、よい強度設計を目指していただければ、著者にとってこの上の喜びはない。
(序文より)

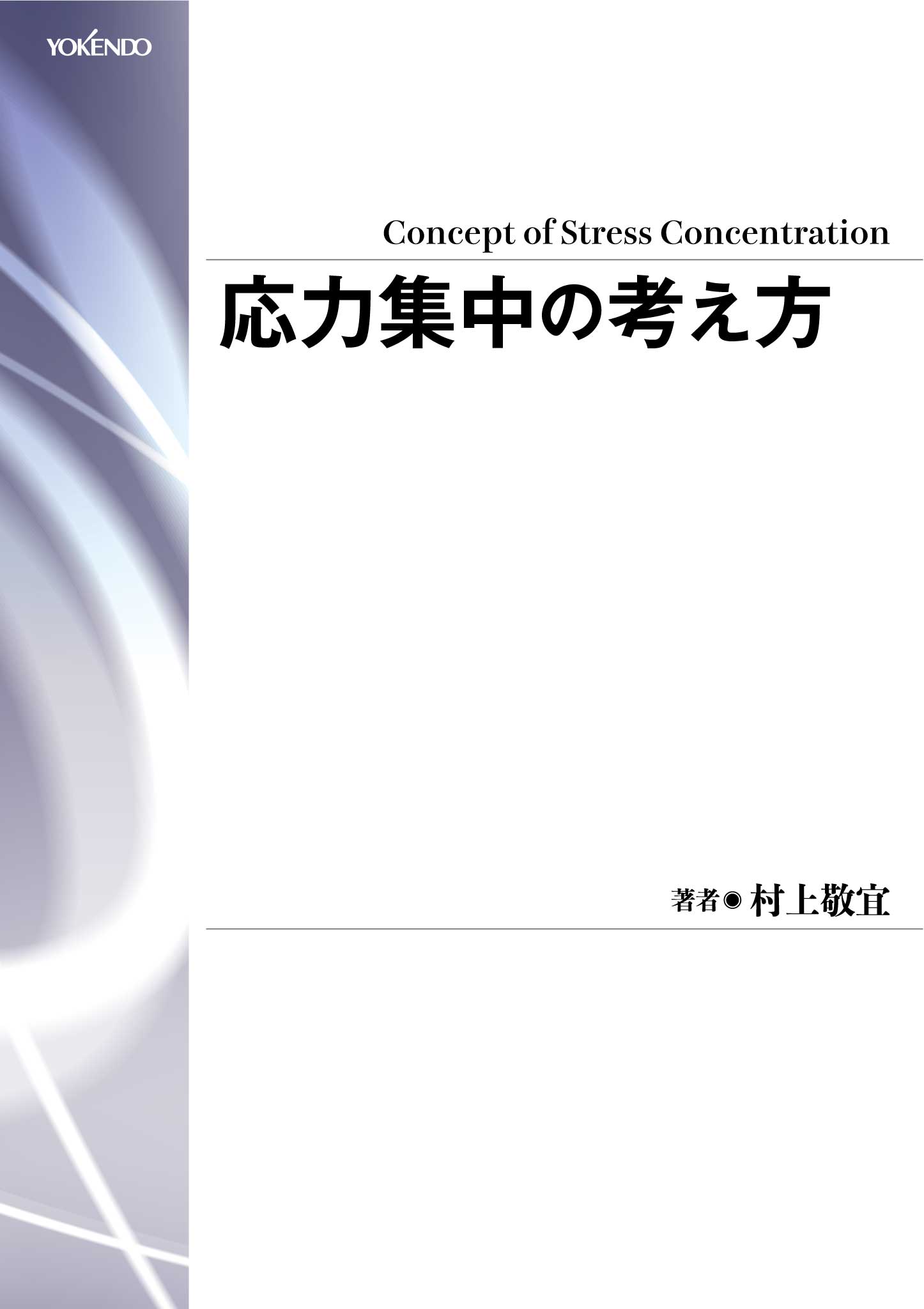
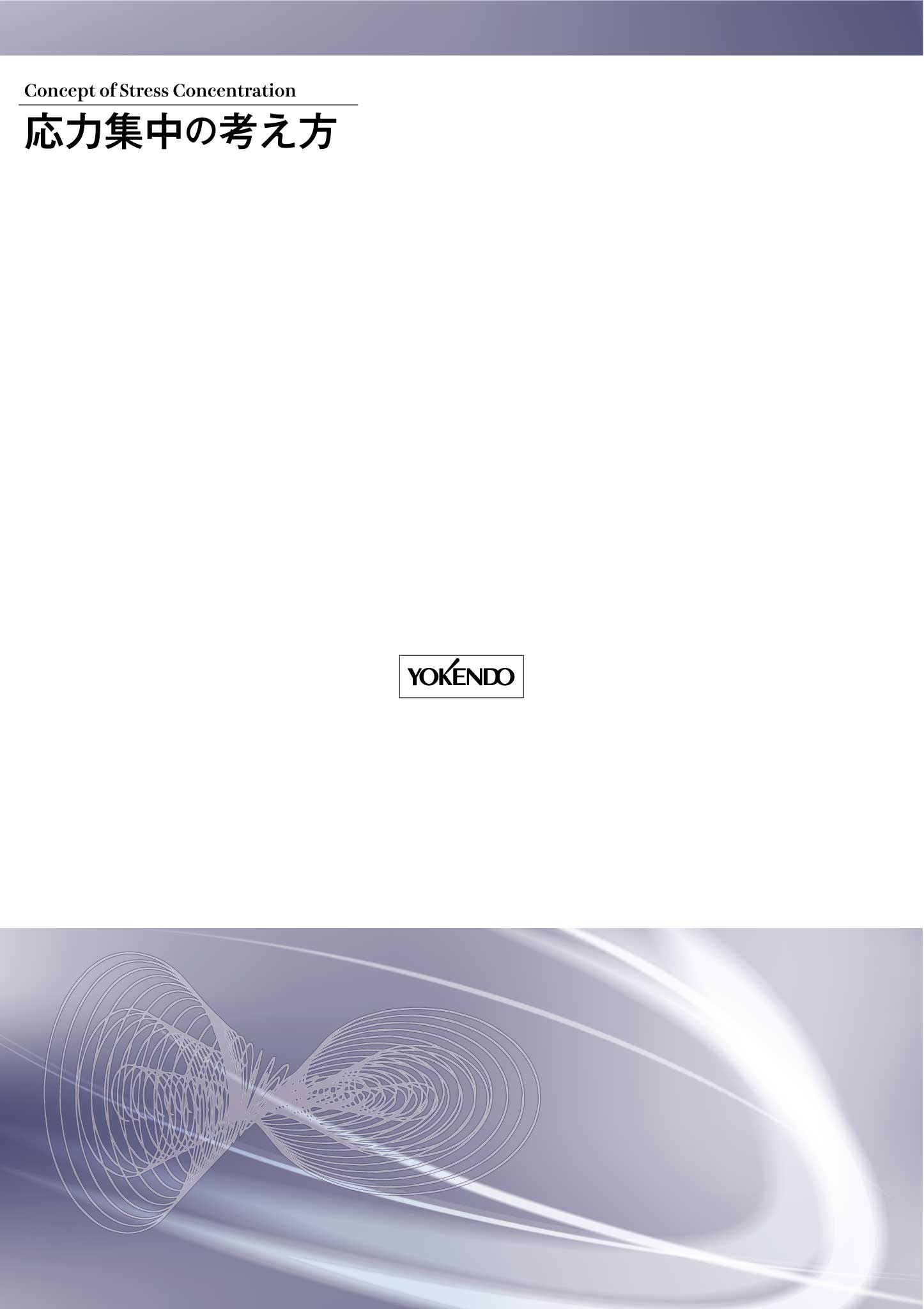
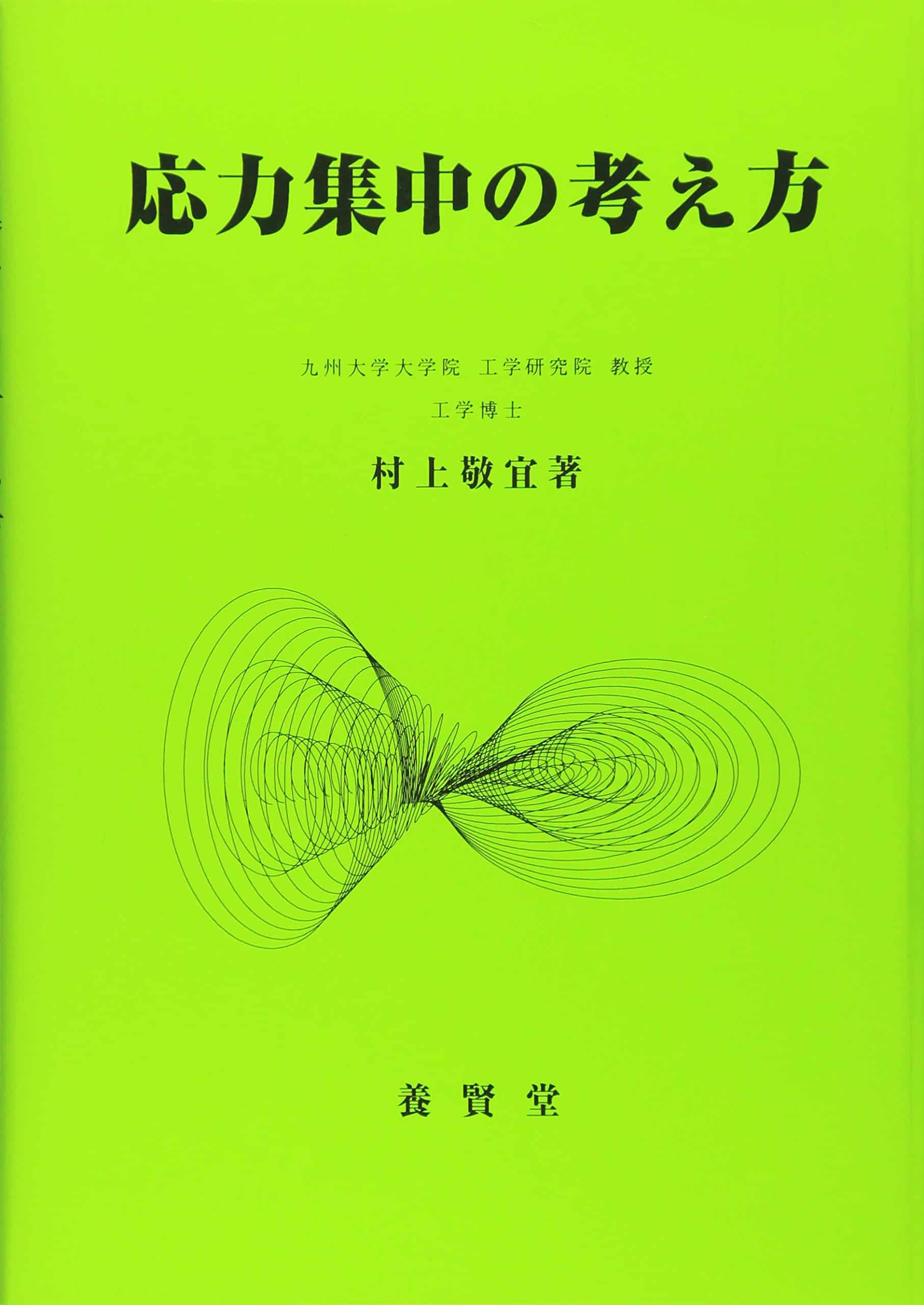

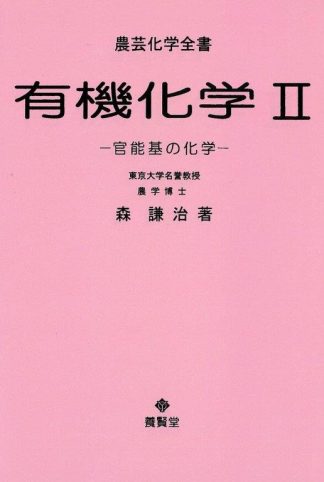











レビュー
レビューはまだありません。