目次
1章 農業経営支援研究の分析視角と接近方法(1.はじめに、2.農業経営支援研究の枠組み、3.農業経営支援研究の課題と対象、4.農業経営支援研究の方法論に関する試論、5.本書の構成と各章の位置づけ)
2章 経営意思決定支援とコンサルテーション(1.はじめに、2.「支援」研究の動向、3.農業改良普及事業における「カウンセリング・コンサルテーション」、4.農業改良普及事業における経営意思決定支援情報システム、5.おわりに)
3章 農業生産・販売過程の外部化と農業サービス(1.はじめに、2.農業経営、市場と農業サービス、3.農業サービスの対象領域と供給主体、4.稲作経営における農業サービス、5.畜産経営における農業サービス、6.花き作経営における農業サービス、7.野菜作・果樹作経営における農業サービス、8.おわりに)
4章 地域農業組織と経営支援(1.はじめに、2.個別農業経営支援と地域農業組織の役割、3.集落営農におけるボランタリー支援の方向と課題、4.地域農業の組織化によるリスク負担の効率化と経営支援、5.おわりに)
5章 農業政策と経営支援(1.はじめに、2.農地制度と農地集積支援、3.農業制度金融と農業投資、4.価格安定制度と経営安定、5.おわりに)、6章農業経営支援研究の到達点と残された課題―編者コメント―(被支援者から見た経営支援論の展開・「支援」の「誰が何をなぜどれだけ誰に」について考える・対称性回復の知としての「支援」・農業政策分析の枠組みの農業経営支援分析への利用)
説明
戦後30有余年、条件不利産業として位置づけられる農業は、産業政策的に見れば一貫して保護すべき対象とみなされてきた。保護するからには管理もする、これが中央政府の変わらぬ考え方であった。その反面、農民たちの創造性、やる気、能力の発揮をいかに引きだすかとか、製品やサービスの最終的な顧客たちのニーズや願いをいかにかなえるかといった問題は等閑視されてきた。
こうした物動主義行政による国家管理システムは、戦後30年を経てすでにほころびを見せていたにもかかわらず、新たな時代精神に適合した農業政策への転換は遅れ、平成4年の「新しい食料・農業・農村の方向」においてはじめてその転換の構図が示され、ついで平成12年の「食料・農業・農村基本法」によってその法定化が実現した。
そこには消費者主権、地域分権・自立、農業者の主体性発揮などの新しい重要な考え方が示されている。このことは政府の役割の後退を意味するが、それは官と民を上下の関係ではなく対等の関係に置くことによって、人々の自己実現や経済社会の活力を引きだすことが可能になると中央政府が表明したことを表している。政府と農業者の関係で言えば、政府が農業者の「自主的な努力を助長する」(農業基本法第5条)のではなくて、「自主的な努力を支援する」(食料・農業・農村基本法第11条)ことを良しとするものである。
ここにおいて、本書のキーワードたる「支援」の真の意味が了解できるようになるであろう。物動主義行政から経営主義行政へ、あるいは管理システムから支援システムへの転換を意味するこの取り組みは、経営相談・研修の実施、農用地利用集積への支援、金融・税制面での特例措置などからなるが、これらを根底から成立させているものは、被支援者たる農業者の経営改善に対する強い意欲、言い換えれば、決断と実行、そしていかなる結果が生じてもその責任は自らがとるのだという自己責任の徹底にあることは言うまでもない。
こうした政策転換がすすめられて以降、農業分野で「支援」という用語を題名に掲げた著書が十冊程度は出版されている。しかし、それらはすべて日常言語としての支援を単純にあてはめているか、さもなければ、はじめに経営支援ありき、といった点から出発しているかのいずれかに属している。本書の最大の特徴は、社会学など他分野におけるこれまでの学問的蓄積に依拠して、支援の定義や分析枠組みから問題の解きほぐしを行っている点にある。その意味で、本書は農業経営支援という問題に本格的にアプローチした最初の試みであると同時に、実践性よりは科学性に重きが置かれているという点にすぐれた特徴がある。
本書の構成については、第1章は農業経営支援における支援とは何か、支援をどうとらえればよいか、といった分析上の基礎理論を提示している。第2章はplan(計画)-do(実行)-see(評価)のマネジメントサイクルのうち、主としてsee→plan過程における経営支援を、農業改良普及事業の側面から論じている。第3章は、上記のマネジメントサイクルのうち、主としてdo過程の経営支援を、外部化と農業サービスの関連から経営部門別に検討している。第4章は地域農業組織における経営支援のあり方を論じている。第5章は農地制度、金融制度、価格安定制度など政策支援のあり方を経営支援の観点から論じている。
本書の出版ははじめの第一歩であって、これを一つの契機として、経営支援という用語を単なる行政用語に終わらせないための研究者のなすべき務めだと思う。

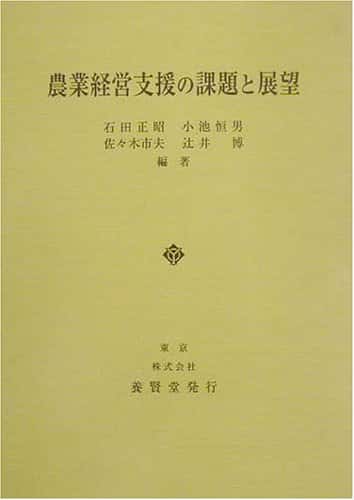
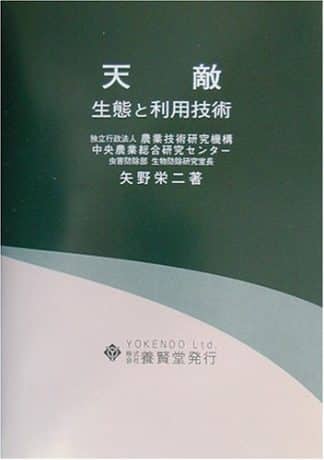

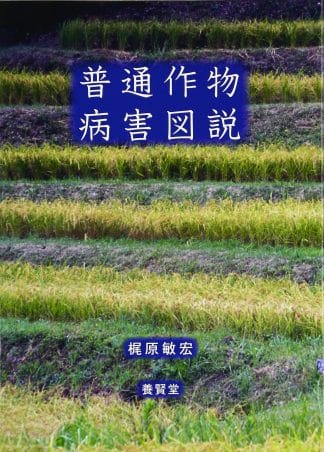
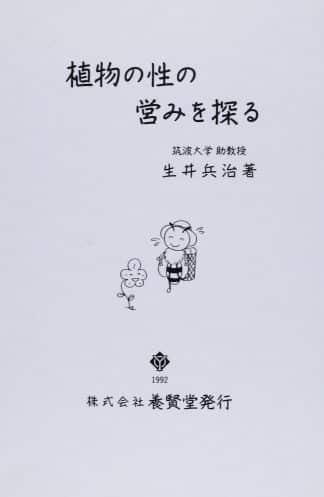










レビュー
レビューはまだありません。