目次
1章 高速遊泳動物の推進におけるダイナミックス
1. はじめに
2. 基礎事項
3. 推進における流体力学の基礎理論
4. 高速遊泳におけるダイナミックスに関する著者らの研究
5. おわりに
2章 6足昆虫ロボットの自律歩行の力学原理
1. はじめに
2. 無限定問題と生命システム
3. 不完結システムとしての多形回路
4. 歩行制御
5. 歩行パターンのシミュレーションとロボットの製作
3章 4足ロボットのダイナミックスと制御
1. 歩容の基本
2. 動的安定性とゼロモーメントポイント
3. 動歩行の軌道計画
4. アクティブサスペンション制御
4章 2足歩行のダイナミックスと制御
1. はじめに
2. 歩行ロボットの機構
3. 運動方程式および衝突方程式
4. 2足歩行システムの角運動量およびZMP
5. 5リンク2足歩行ロボット
6. 倒立振子モデルによる解析
7. パッシブ(受動)歩行ロボット
8. 歩行制御の方策
9. 歩行ロボット
10. 2足歩行ロボットに関する各種研究
11. おわりに
5章 顔ロボットにおける表情表出の力学と制御
1. はじめに
2. 顔ロボットの設計
3. 顔ロボットの全体構成
4. シリコン顔皮膚の製作と取り付け
5. 顔ロボットでの静的顔表情の表出
6. 顔ロボットによる動的な表情表出
7. まとめ
索引
説明
18世紀の蒸気機関の発明から、紡織機、自動車、飛行機、ロボットへの発展を眺めると、機械システムは「社会淘汰」の圧力を受けて進化している。
これまでの機械システムの設計は、設計仕様を与え、それを満足する機械要素を選定しシステムとして構成することといえよう。
機械システムは与えられた設計仕様の条件の中で運転しているときは、その機能を発揮するが、ひとたびその仕様から外れた条件では、その機能が十分にまたは全く発揮できないという問題が常に存在した。
機械システムと環境とのインターラクションにおいて、環境の変化に応じて機械のシステム構成を変化し、仕様の機能発揮が可能になるであろうか。
機械システムの機能のロバスト性の向上は工学の大きな課題であり、また永遠の課題である。
設計された人工物システムが設計仕様の枠外でも機能することの可能性を考えると、その問題解決として、視野を生物システムに向けることを思いつく。
それは、生物システムが物理的身体を持ち環境の中で活動し、長い時間の経過の中で激変する環境に生き延びてきていること、すなわち、生物としての機能を発揮し続けていることを知っているからであろう。
「生物に解を求める」ことは、生物を真似するのではなく、生物システムの機能発現のメカニズムを知り、そこにある構成原理を知ること、その構成原理を実現する設計原理を確立すること、そしてそれを人工物でつくる工学システムの構築へと拡張・普遍化することであろう。
以上の視点から、工学システムの新しい構成、すなわち、その形態構成、ダイナミックス、および制御の構成原理を求めて、生物システムに学ぶことの大切さを本書で提唱している。
本書は、「生物型システムのダイナミックスと制御」と題して、魚を代表とする遊泳動物、昆虫のような6足動物、犬や馬のような4足動物、人間を代表とする2足動物における「運動機能」についてのダイナミックスと制御、そして人間の顔表情を代表とする「情報機能」における力学と制御について、斯界の第一人者が執筆している。
本書は「生物型システムのダイナミックスと制御」に関心を持たれる研究者や大学院生さらには、新しい人工物システムの構成原理の開拓に関心をもたれている研究者に手にしてもらいたい。

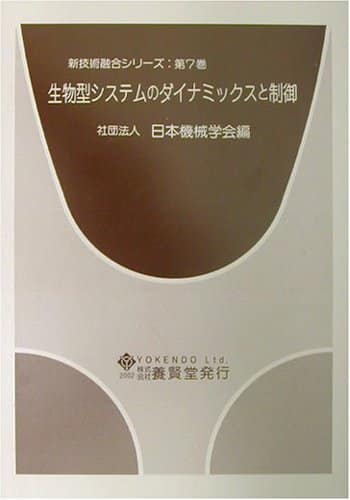
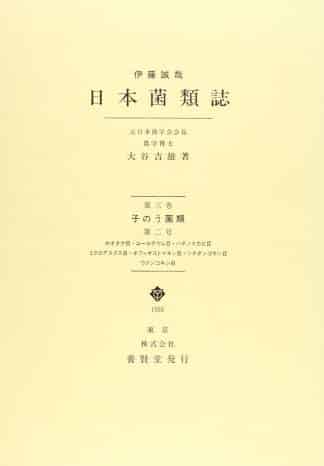












レビュー
レビューはまだありません。