目次
連載講座
パリ協定以降の世界と日本のエネルギー動向(25)
再生可能エネルギー(海洋発電)の課題と展望 その1
一般財団法人 航空宇宙技術振興財団 評議員
伊藤義康
産業安全工学(31)
設計リスク管理と安全性(2)
有明工業高等専門学校 創造工学科 教授
堀田源治
CFDの基礎講座(28)
衝撃波捕獲スキームの基礎 前編
慶應義塾大学 名誉教授
棚橋隆彦
詳しく学ぶ ねじ締結の基礎(14)
酒井ねじ締結相談室 室長 工学博士
日本機械学会フェロー
酒井智次
機械構造用金属材料の超高サイクル疲労(24)
6. VHCF–2~VHCF–4の10年間の研究動向(4)
立命館大学 名誉教授
酒井達雄
サウンドデザイン論(11)
音をデザインし製品価値を高めるには
広島市立大学 教授
石光俊介
データで学ぶ 超耐熱合金切削の基礎技術とトラブル対策(15)
第5章 エンドミル切削の基礎技術(3)
ものづくり人材育成塾 難削材切削技術研究所
狩野勝吉
コラム:一杯のコーヒーから(160)
知について考える(その1) ―本能をもっと活用しよう―
Stanford University visiting professor
慶應義塾大学 顧問
福田収一
工学・工業界ニュース
説明
巻頭記事「パリ協定以降の世界と日本のエネルギー動向(25)」
2011年から、経済産業省や環境省により波力や潮力などの海洋エネルギーを利用した発電システムの開発と実証試験が進められてきた。
実用化時に発電コスト 40 円/kWh 以下を達成目標とした実機開発が主体である。
しかし、太陽光発電や風力発電に比べて割高であるため、現在は発電コスト 20 円/kWh 以下を目指して、
発電効率の向上、設置コストの低減、海洋環境での耐久性向上などの技術開発が進められている。
また、世界全体でみると海洋エネルギー発電の導入量は、2010 年で 52.6 万 kW(波力:0.32 万 kW、潮汐:51.8 万 kW、潮力:0.52 万 kW、海洋温度差:0.03 万 kW)である。
中でも、欧州(EU)は波力発電や潮力発電の商業化に積極的に取り組み、欧州海洋エネルギー協会によれば発電容量として 2020 年に 360 万 kW(全発電電力量の 0.3 %)、
2050 年に 1 億 8 800 万 kW(全発電電力量の 15 %)への急増が予測されている。
2010 年頃の陸上風力発電の普及期から約 10 年経過し、2020 年頃には洋上風力発電の普及期が到来する。
本稿で紹介する海洋エネルギー発電は、さらにその 10 年後である 2030 年頃に本格的な普及期が見込まれている。
本稿では海洋エネルギー発電の仕組みとポテンシャルと、普及促進の取組み、
市場動向、メーカーの開発動向について、具体的な事例を示しながらまとめる。
一般財団法人 航空宇宙技術振興財団 評議員
伊藤義康


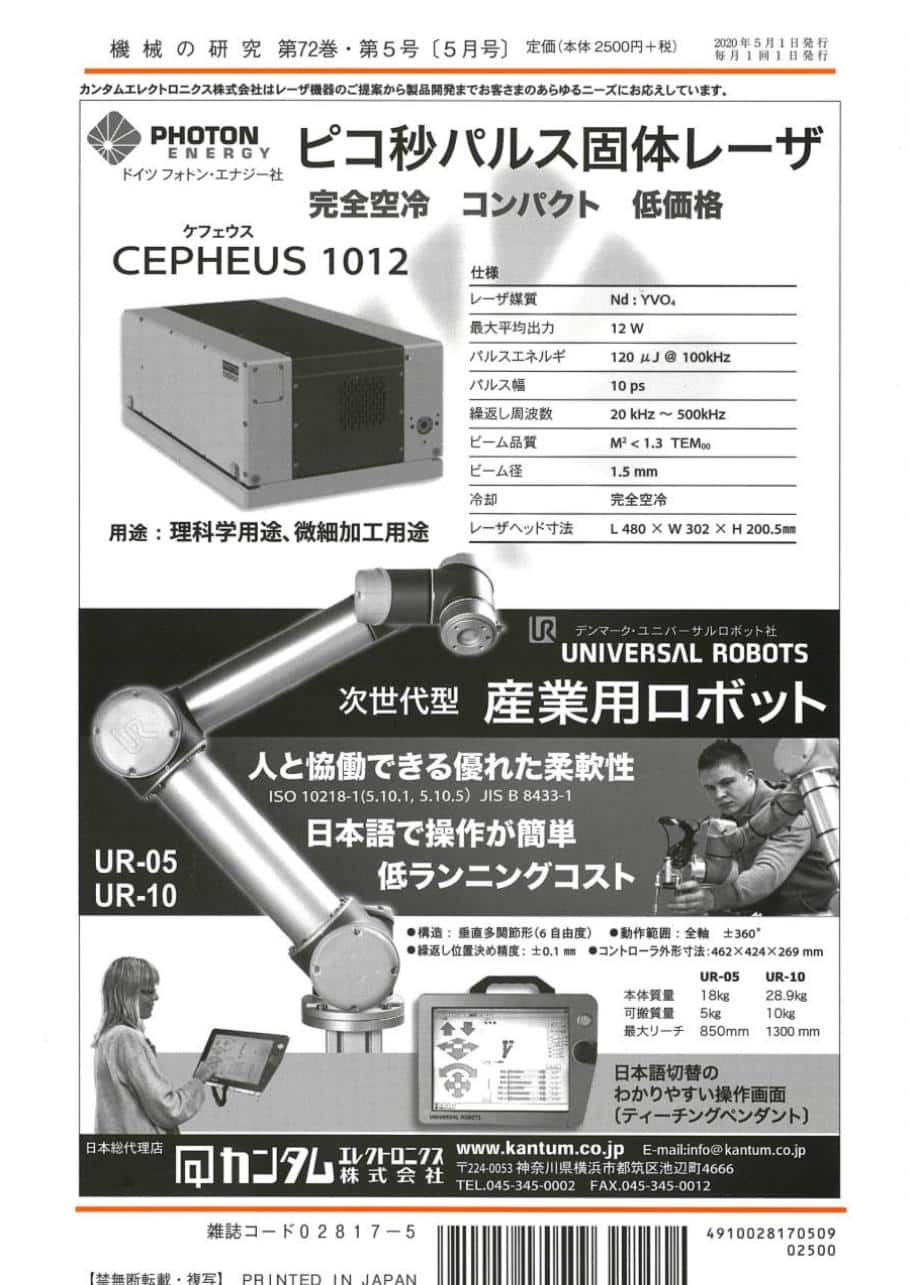















レビュー
レビューはまだありません。