目次
1.「ものづくり」を「生物」に学ぶ視点
2.生物の特徴
2.1 生物の特徴とは
2.2 構造・組織の特異性
2.3 生殖・発生
2.4 遺伝・進化
2.5 エネルギーとその変換システム
2.6 社会性・活動規範
3.ものづくりとは
3.1 工学的設計とその過程
3.2 バイオニック・デザイン
4.生物の特徴とそのからくりの例
4.1 柔剛合わせもつ竹の秘密
4.2 外部に強く,内部に弱い卵の秘密
4.3 軽量で耐火性のある桐の秘密
4.4 繰返し衝撃負荷に耐える啄木鳥の秘密
4.5 スーパー長寿命な銀杏の秘密
5.生物のものづくりの特徴
5.1 ものづくりにおける普遍的特徴
5.2 自然環境への適応能力・適応機能
5.3 多目的・多機能な構造・組織
5.4 省資源・省エネルギーシステム
5.5 構造・組織の形成方法
6.生物に学ぶ設計法
6.1 生物のものづくりから何を学ぶか
6.2 遺伝的アルゴリズムとその応用例
6.3 セルラ・オートマトンとその応用例
6.4 Lシステムとその応用例
6.5 ニューラルネットワークとその応用例
参考文献
索引
おわりに
説明
「生物に学ぶものづくり」 の視点としては、まず多種・多様な生物に対して、それらに共通する設計原理的なものを抽出し、そこから工学へ利用できるものを発見する立場がある。もう一つは生物の多様性に注目すること、すなわち個々の生物がその与えられた特異な環境下で、如何に巧みに生き、子孫を繁栄させているかについて、個々の生物の能力・行動、機構・システム、材料・組織などを解明し、そこから工学へ応用できるものを発見する立場である。
本書では、まず後者の立場から著者がこれまで興味をもって分析してきた、竹、卵、桐、啄木鳥、銀杏の五つの生物事例の主として力学的視点からの興味深い話題を提示したつもりである。これらの結果から、複合材料のような材料設計上の具体的知見や、繰返し衝撃負荷を受ける機器の構造設計上の具体的知見などが明らかとなった。しかしもっと重要なことは、これら数少ない五つの生物事例を通してさえ、上述の第一の視点としての多様な生物に共通して見られる 「ものづくりの特徴」 が抽出できたことである。それを改めて示すと、次のとおりである。
① 変化する自然環境への適応能力・適応機能
② 多目的・多機能な構造・組織
③ 省資源・省エネルギーシステム
④ 構造・組織などの形態・質・量の変化
⑤ 材料・構造などの組合せの多様化
⑥ 機能終了時への対策
本書では、さらにこれらの特徴が現れてくる機構、すなわち 「生物における ものづくりの基本的なメカニズム」 にも注目した。その結論として、次の二つが最も重要であることを述べた。
(1) 生物における進化のシステムの存在
(2) ものづくりにおける細胞の働きの重要性
(1) の進化のシステムこそ、時間的にも空間的にも多様に変化する自然環境下で膨大な生物が生存する現状を可能にしたものである。
その進化の原理は、DNAの交差、突然変異などによる世代交代の進化システムと、脳細胞などの学習進化による世代内の進化システム(環境適応システムと考えてもよい)が存在している。そして、これらを現実に可能としているのが(2)の細胞機能であり、細胞こそ生物創造の基本であり、かつすべてであるといえる。
したがって、これを真に模倣する工学的技術の生まれることが 「生物に学ぶ ものづくり」 の本質と考えられる。現状ではその道ははるかに遠いが、細胞が行っている一部の機能のみを利用した最適化のアルゴリズムや形態形成システムが提示されているので、「生物に学ぶ ものづくり」 の例としては、少々おこがましいが、その使い方のいくつかを紹介した。
以上述べたように 「生物に学ぶ ものづくり」 への道はまだまだ遠い。ただ、上述したように、生物自身、変化する環境に適応進化するシステムを有しているのだから、工学に携わる者はそのための努力を惜しむべきではない。このことと関連して本書が読者の方々に何かお役に立てば幸いである。

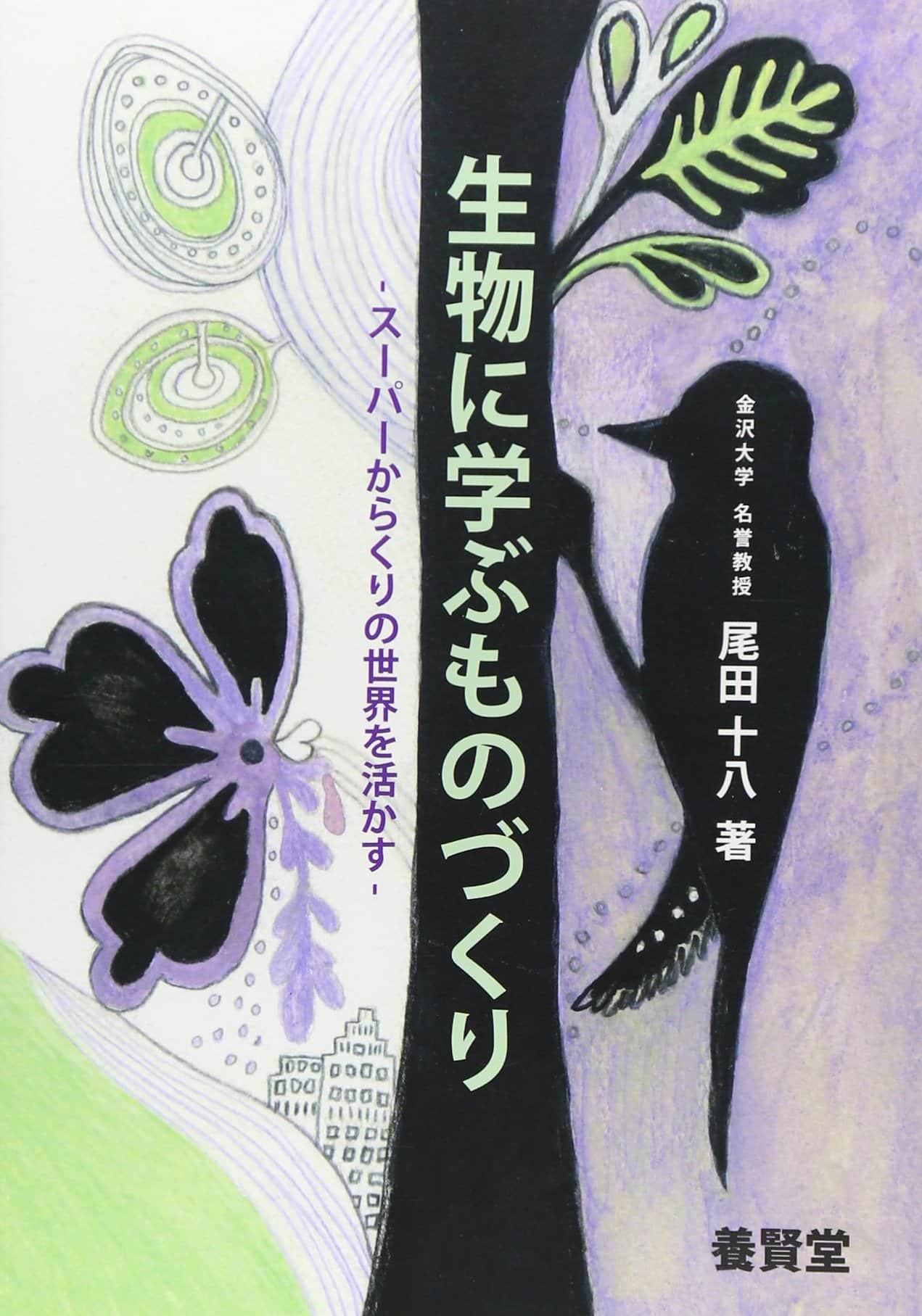
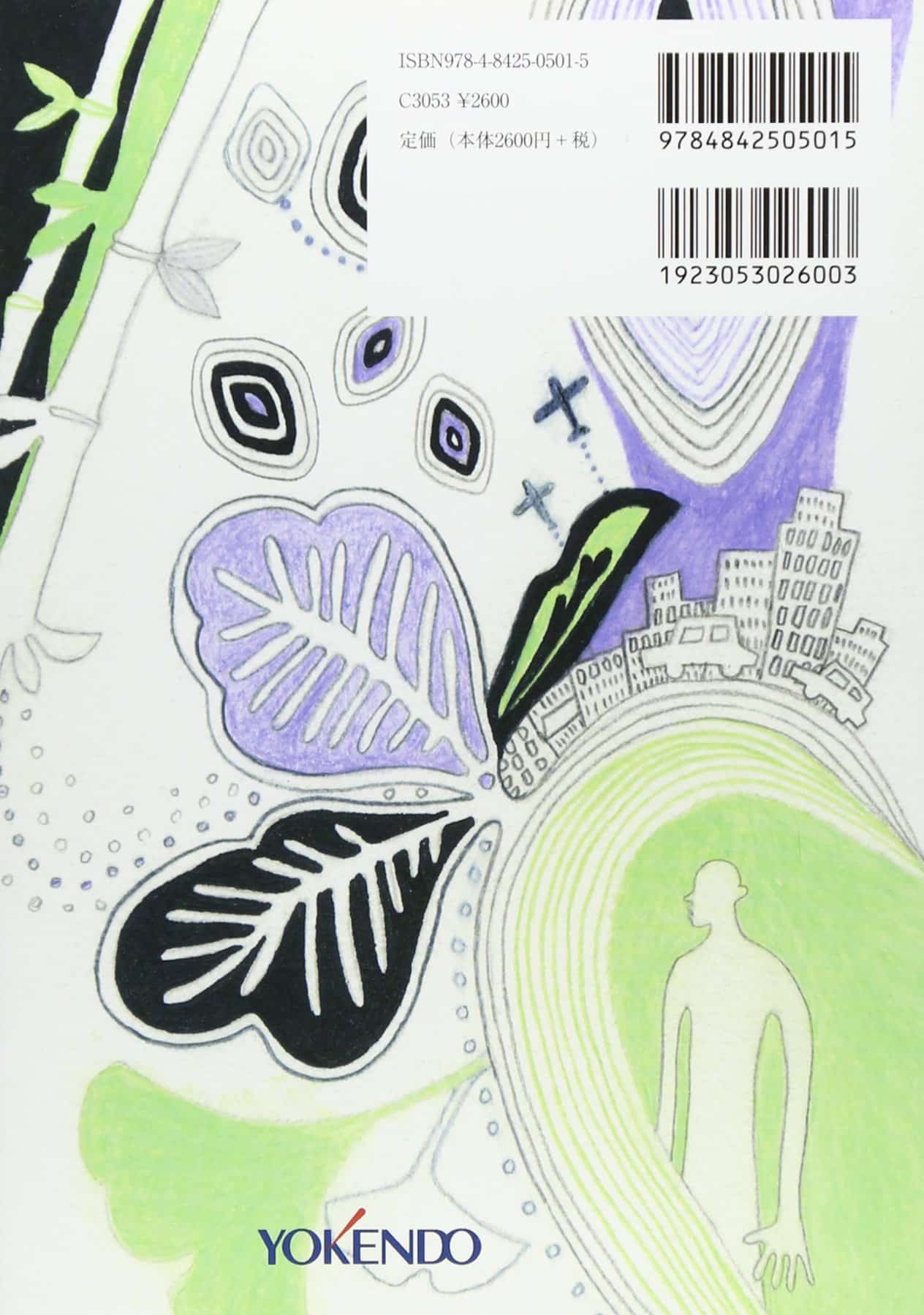
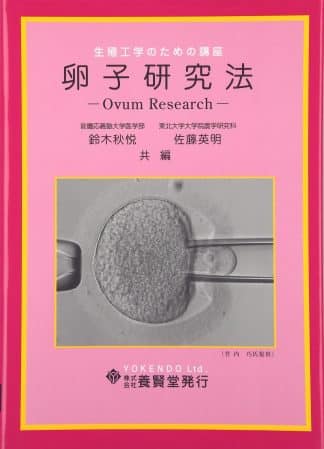
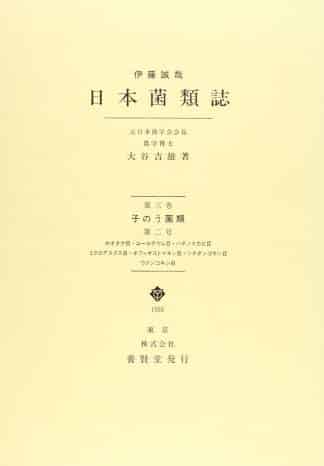











レビュー
レビューはまだありません。