目次
第1章 湿地における生物多様性と水生植物の生態
1.湿地の定義
2.湿地の機能の歴史的背景
3.湿地環境の多様性と植物の生態特性
4.湿地における野生植物の生態
5.水生植物の生態と栄養吸収機能
6.水生植物の光合成
7.水生植物の生存戦略
8.マングローブの生態
第2章 湿地の土壌資源
1.湿地土壌の物理的・化学的特性
2.湿地土壌の微生物
3.湿地土壌の生産性と持続性
第3章 作物の嫌気応答のメカニズム
1.冠水抵抗性イネの開発と課題
2.イネの冠水抵抗性と生存戦略
3.冠水条件におけるイネの発芽期および幼植物期の応答と適応
4.過湿土壌に対する作物の応答と適応機構
第4章 作物の冠水害・湿害
1.イネ
2.麦類
3.トウモロコシ
4.ダイズ
5.野菜
6.果樹
7.牧草
第5章 気候変動と洪水
1.気候変動と冠水害
2.耕地洪水発生のメカニズムと特徴
3.衛星画像を利用した冠水・洪水被害の把握
第6章 湿地における洪水被害と作物栽培技術の活用
1.わが国における洪水とその農業被災
2.わが国における治水の歴史
3.アジア地域における洪水環境と洪水を活用した作物栽培
4.アフリカ地域における洪水を利用した低湿地氾濫原稲作
5.湿地帯でのイネ栽培と塩害
6.湿地における農業土木工学技術
7.栽培技術の改善による湿害の軽減
索引
説明
湿地(wetland)とは、永続的または周期的に地面が浸水することによって成り立っている生態系と定義され、そこに生息する植物は、低酸素あるいは無酸素条件(嫌気条件)に適応性(嫌気応答性)を有するものが多く含まれている。湿地は、河川の源流から、湿原、沼地、干潟、マングローブ林など沿岸地域まで広く分布している。湿地は、多様な機能を有しており、適切に保存していくことが必要とされているが、一方で、湿地の水資源を農業に有効的に利用し、作物生産の向上に貢献することも重要である。湿地は、地形的には貯水、土壌浸食の軽減、有害物質の除去、耕地劣化の防止、生態的には野鳥や植物の保全、経済的には農村共同体の活動への貢献など様々な機能を果たしている。我が国の農業においての湿地は、水田が代表的であるが、水田が上記のような多面的機能を担っていることは良く知られている。このように世界的に広く分布する湿地環境を維持しつつ農業生産に利用していくことは、今後も引き続く地球規模の食料不足の解消に重要であると考えられる。
地球上の人間活動による温室効果ガスの排出が、気温上昇を招いていることは良く知られており、今後温暖化により降水量や降雨パターンが大きく変化し洪水や旱魃が頻繁に発生することが予測されている。実際に、異常気象が世界各地で頻発しており、大規模な洪水、旱魃が人間の生活のみならず農業にも大きな損失を与えている。
米はアジアにおける主要穀物の一つであるが、東南・南アジア地域では毎年のように洪水が発生し、イネの生育に影響を及ぼしている。一方、アフリカ地域においては、未利用の低湿地にイネを導入する試みも始められている。我が国では、水田の高度利用を目的とした転換畑への畑作物の導入が進められ、食糧自給率の向上が図られているが、転換作物として導入されたコムギ、ダイズやトウモロコシなどの過湿害による収量の低減と品質の低下が、普及の大きな足枷となっている。こうした畑作物の過湿害は、モンスーン地域の多雨期に限らず、半乾燥地の一部地域においてもしばしば発生する問題である。このように、冠水・過湿によるストレス下で植物の生育を維持し生産を確保する事は、国内外の作物生産にとって重要な課題であり、そのためには耐性や回避に関わるさまざまな機能を改善して、環境適応性を向上させることが必要である。
湿地環境においても生育が可能である水生植物を参考に、過湿耐性メカニズムを解明することは、作物の湿地環境適応性の向上を図る上で有効な方策である。最近イネにおいては、冠水に対する耐性遺伝子の詳細が明らかになるなど、イネの耐性向上に密接に関連した研究開発が推進されている。畑作物についても、近縁種のなかには過湿環境への高い耐性を備えた種が存在する事が知られており、それらの特性と関連する遺伝子を解明することが、作物の過湿耐性の改善につながると期待されている。さらに、我が国では、秋落ち水田における不耕起栽培や畝立て稲作、転換畑における排水技術などの有効な栽培・土木技術が開発されている。このように、嫌気条件下での植物および作物の有用形質の解析とその利用、また適正な栽培技術の応用は、作物の安定的生産体系の維持において重要であり、今後のさらなる研究の推進が望まれている。
本書の目的は、過湿あるいは冠水を特徴とする湿地環境における作物生産の向上に貢献するため、湿地に関わる農業生態学的観点を中心に、遺伝育種、栽培生理、土壌肥料等までに及ぶ有用な情報および技術を広く関係者に提供することであり、以下のような構成となっている。まず、世界的な湿地環境を概観し、湿地の機能や多様性またそこで生息する水生植物等の生態について解説、次に、湿地土壌資源についてその特徴を紹介、さらに、過湿・冠水等湿地条件に適応した作物の嫌気応答メカニズムの特徴や耐性強化に必要な機能について、作物の湿害・冠水害とあわせて解説、そして、世界的な気候変動と洪水発生の関係について述べた後、終わりに湿地における有用な対策技術について論じている。
我々は環境に調和しながら作物生産を向上させるという一見矛盾とも思えるテーマを背負っている。この点からも、湿地環境と作物生産の関係について、現時点での理解を多角的に総括することは重要である。本書が湿地の理解を深め、また近い将来に我々が遭遇するであろう世界的な食糧危機の解消に少しでも役立つことができればと願う次第である。

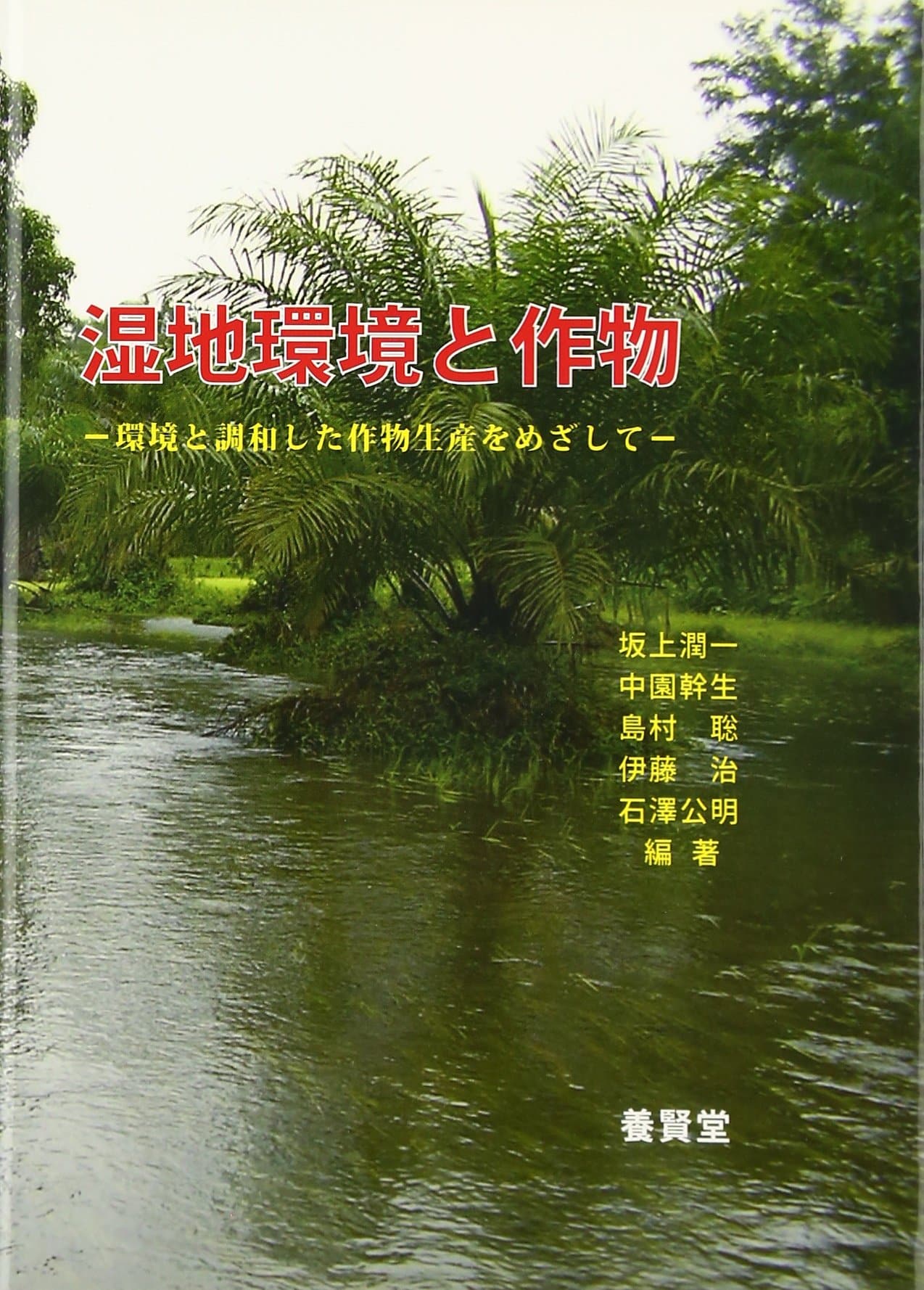
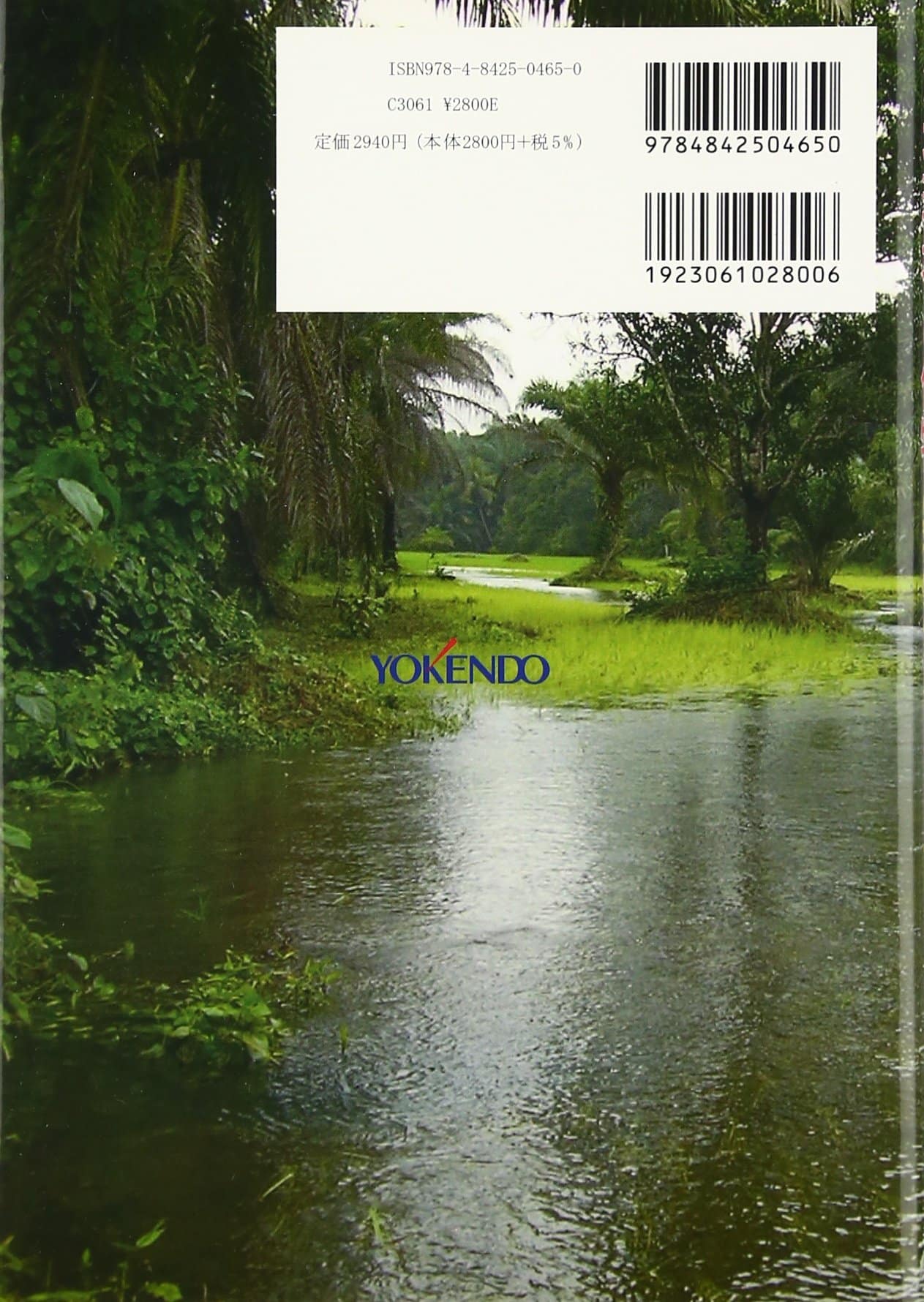
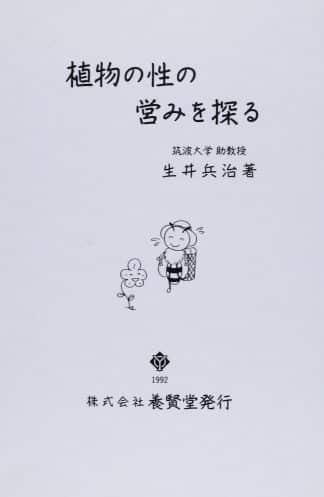
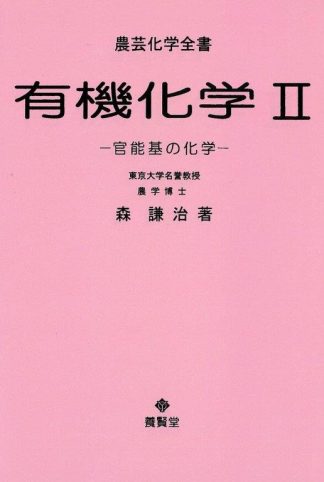

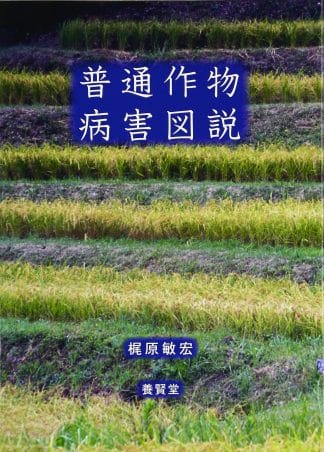
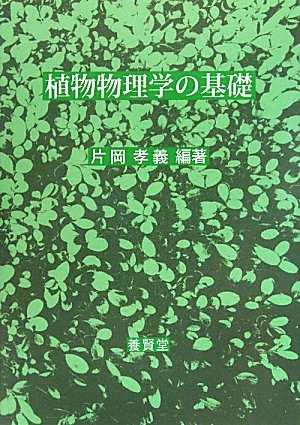










レビュー
レビューはまだありません。