目次
第1章 破壊力学の基礎(1. 破壊力学の概念:2. き裂の解析:3. 応力拡大係数の様々な解析法)
第2章 破壊強度を支配する力学パラメータ(1. 応力拡大係数と破壊靭性値:2. き裂開口変位の限界値:3. き裂先端塑性域の限界値:4. ストレッチドゾーン寸法:5. J積分の限界値:6. 破壊靭性に影響を及ぼす諸因子)
第3章 疲労破壊(1. 高サイクル疲労と低サイクル疲労:2. 疲労強度に及ぼす平均荷重の影響:3. 疲労き裂:4. き裂伝ぱ速度に及ぼす力学的な要因:5. 破壊力学に基づくき裂材の寿命解析:6. き裂材の疲労強度に及ぼす環境の影響:7. 耐疲労損傷設計の概念)
第4章 フラクトグラフィ(1. 破面観察の方法:2. 破面の巨視的様相:3. 破面の微視的様相と分類)
第5章 非破壊検査(1. 非破壊検査技術のいろいろ:2. 代表的な非破壊検査法の欠陥検出精度:3. 非破壊検査におけるヒューマンファクタ)
第6章 破壊の事例と防止策(1. 事故原因のあらまし(航空機の例):2 荷重見積もりの甘さによる事故事例と対策:3. 固有振動に関する知識不足による事故事例と対策:4. 材料と環境の相性の問題による事故事例と対策:5. 腐食および防食:6. 設計不良に伴う応力集中による事故事例と対策:7. 熱処理の不適正による事故事例と対策:8. 大規模修理・設計変更後の構造モニタリング不足による事故事例と対策:9. 検査の見落とし・省略、マニュアル無視整備による事故事例と対策:10. 評価試験のまずさに基づく事故事例と対策:11. 機械の目的外使用による事故事例と対策:12.「失敗の樹」解析のすすめ)
参考文献:索引
おわりに
説明
安全(safety)・安心(security)の確保は、人々の社会生活において最も基本的なものである。社会生活を営むうえで必要不可欠な様々なハードウェア(陸海空の交通システム、各種プラントからICチップに至るまで)の安全・安心を支えるための中心となる学問が破壊力学である。形あるものは、いつかは必ず故障し、壊れる。損壊の原因は、疲労、腐食、過大荷重など様々であるが、構造システムが運用期間内に予期せぬ原因で破壊してしまうことがあってはならない。そのため、構造システムの設計者には破壊力学に基づいて様々な使用環境を想定した耐久設計を行うことが求められる。
一般に、破壊力学の重要性は認識されるものの、破壊力学および構造健全性の様々な分野に関わる初心者、中堅技術者から経営者に至る多くの人達が「樹を見て森を見ず」のたとえではなく、「樹も森も同時に見える」ように解説した書物は見当たらないのが現状である。そのため、本書では破壊力学がカバーするほとんどすべての分野について深くまたわかりやすく解説し、広範な読者の満足が得られるように心掛けて編集した。
第1章では、き裂問題を中心とした破壊力学の原理と基礎理論について述べる。
第2章では、第1章の理論解析によって得られるき裂の特異場を表わすパラメータであるK値あるいはJ値に基づく破壊靭性値、CTOD、塑性域寸法の限界値など材料強度の立場から見た破壊強度特性値、およびそれらの実験的求め方、材料特性値としての破壊靭性に及ぼす諸因子の影響について論ずる。
第3章では、疲労問題を取り扱う。低サイクル疲労、高サイクル疲労、疲労設計線図、累積疲労損傷則、ランダム疲労および疲労強度に及ぼす平均応力の効果について解説する。また、疲労き裂の問題に関して、進展のメカニズム、進展速度に及ぼす残留応力や過大荷重などの力学的因子、および腐食、応力腐食割れなどの環境因子の効果、き裂開閉口挙動の概念についても紹介し、さらに解析の応用例として破壊力学の手法に基づく寿命評価事例について詳述する。
さらに、いくつかの代表的な耐疲労損傷設計の概念、および損傷許容設計概念に基づいた構造健全性確保のための具体的事例について紹介する。
第4章では、破壊原因調査に必要なフラクトグラフィについて、破面の形成メカニズム、巨視的および微視的な破面の見方について解説する。
第5章では、構造の健全性を評価するために不可欠な各種の非破壊検査技術について、それらの特徴および検査結果に影響を及ぼす検査員の要因などについて論ずる。
第6章では、構造・材料に起因した破壊事故を防止する目的で、国内外で発生した主要な事故の事例を原因別に分類し、事故原因、事故の教訓、再発防止のための対策について個別的また総括的な観点から解説する。

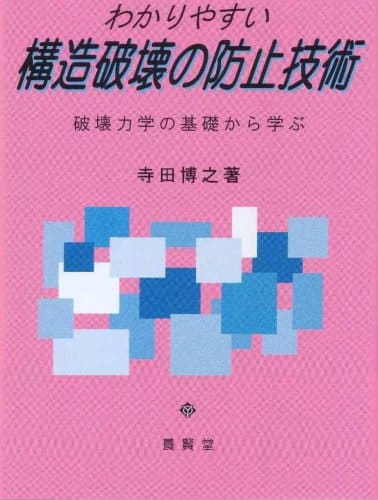

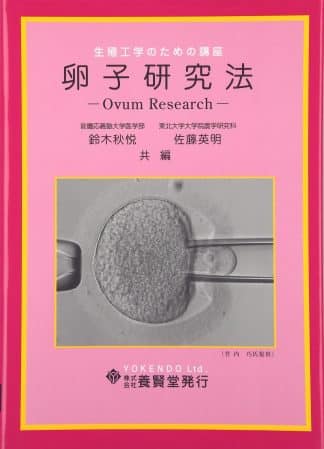
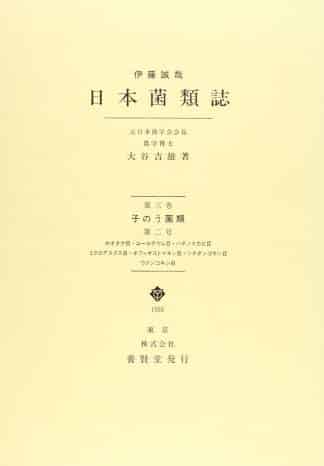











レビュー
レビューはまだありません。