目次
第1章 研削抵抗の発生メカニズムと研削方式による形態変化
1.まえがき
2.砥粒の切削抵抗
3.砥石の研削抵抗
4.研削方式による研削抵抗の発生形態
5.あとがき:参考文献
第2章 ひずみゲージ法による研削抵抗の計測技術とトラブルシューティング
1.まえがき
2.ひずみゲージ法
3.研削抵抗の検定とデータ処理
4.トラブルシューティング
5.あとがき:参考文献
第3章 研削抵抗分布の最先端計測技術
1.まえがき
2.研削抵抗分布の計測法
3.その他の最先端計測技術
4.あとがき:参考文献
第4章 熱電対埋込み法による研削温度の計測技術とそのノウハウ
1.まえがき
2.研削温度の発生メカニズム
3.熱電対埋込み法
4.あとがき:参考文献
第5章 接触式表面温度計による研削温度の計測技術
1.まえがき
2.接触式表面温度計による計測
3.赤外線温度計とサーモグラフィー
4.あとがき:参考文献
第6章 工作物の熱変形量に関する計測技術
1.まえがき
2.熱変形量の急速バック計測法
3.インプロセス予測計測法
4.あとがき:参考文献
第7章 タッチセンシング技術
1.まえがき
2.加工能率向上に対する加工点検出の必要性
3.データに埋もれた真実を見出そう
4.タッチセンサの構成と間隔検出方法
5.タッチセンシング機能の発現
6.タッチセンサの信号特性
7.実用タイプのタッチセンサ開発指針
8.あとがき:参考文献
第8章 表面粗さ計による表面プロフィルの測定法と砥石摩耗量の求め方
1.まえがき
2.3次元表面プロフィルの測定法
3.円筒面プロフィル測定における母線の割出し
4.砥石摩耗量の測定
5.あとがき:参考文献
第9章 砥石台移動量と寸法生成量ならびに切残し量の計測技術
1.まえがき
2.熱変形量を考慮した干渉状態
3.砥石台移動量と砥石摩耗量
4.軸剛性に起因する切残し量
5.実寸法生成量の計測技術
6.熱変形量による実研削現象
7.あとがき:参考文献
第10章 顕微鏡による仕上げ面の観察と仕上げ面特性の評価技術
1.まえがき
2.各種顕微鏡による観察の特徴
3.レプリカ法を利用した仕上げ面の観察
4.SEMを利用した仕上げ面特性の定量的評価法
5.仕上げ面特性と加工変質層の評価法
6.あとがき:参考文献
第11章 砥石表面の観察技術と砥石干渉形態の解析技術
1.まえがき
2.レプリカ法を利用した砥石表面の観察技術
3.砥石干渉形態の評価技術
4.あとがき:参考文献
第12章 研削実験の手順と安全対策
1.まえがき
2.研削実験の意外なポイント
3.安全な実験のためのNG事例
4.あとがき:参考文献
索引

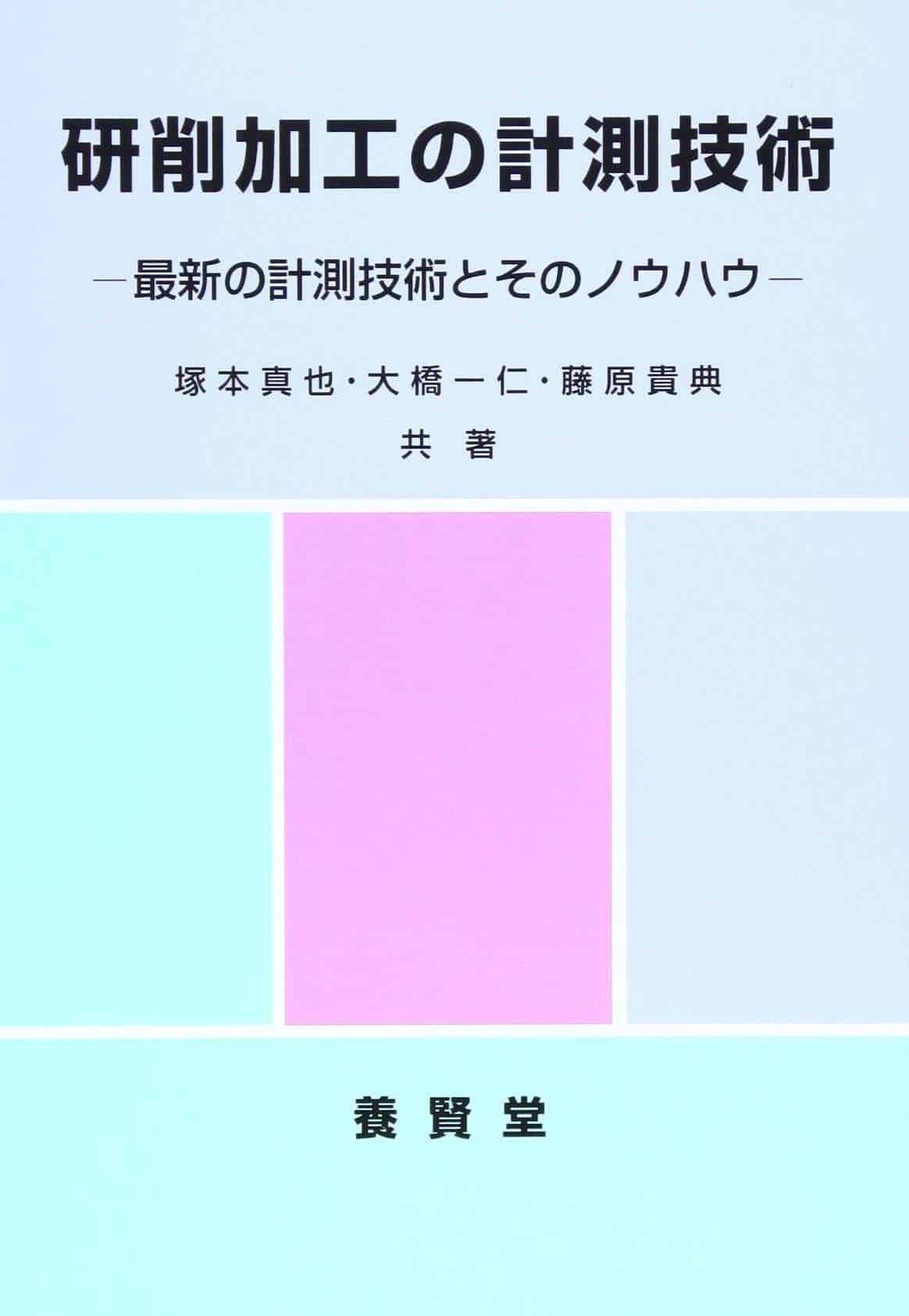

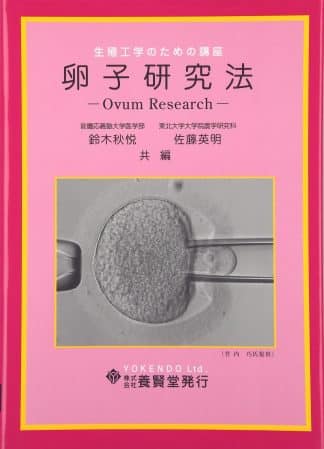










レビュー
レビューはまだありません。