目次
1章 トライボ要素の損傷
1.はじめに
2.トライボ要素の損傷と経済問題
3.トライボ要素の損傷と環境・エネルギー問題
4.トライボ要素の損傷の調査法
2章 トライボ要素の損傷例とその対策
1.すべり軸受
2.転がり軸受
3.歯車
4.密封装置
3章 トライボシステムにおける損傷例とその対策
1.自動車、内燃機関における損傷例とその対策
2.製鉄における損傷例とその対策
3.工作機械およびプレス機械における損傷例とその対策
4.各種産業機械における損傷例とその対策
5.情報機器における不具合例とその対策
6.特殊環境機器における不具合例とその対策
4章 損傷予防の方策
1.損傷予防のための諸技術
2.潤滑剤による方策
3.材料による方策
索引
説明
通常「潤滑」は相対運動面の円滑な作動を実現するソフトウエアとしての技術体系を総称する用語であるが、同時にトライボロジーという学問分野の名称が今日のように一般に用いられるまで、円滑な作動という範疇の枠外にあった多くのトライボロジー関連の現象をも慣用的に包含してきた用語でもあった。一方、「故障」は、ハードウエアである機械及び機械要素に生じる正常でない作動状態を意味する用語であり、「潤滑」と「故障」とを結合して考え出された「潤滑故障」は「トライボロジー」が一般に普及していなかった時代における熟慮による所産であったのであろう。しかしながら、「トライボロジー」という用語は、世に出てから3分の1世紀を経過して、機械工学はじめ関連の学問分野ですでに定着したと判断できる状況になった。 機械要素・機器類の正常でない作動状態を意味する用語として、「故障」以外に、「機能低下」、「損傷」、「不具合」などがある。転がり軸受では、疲労限以上の荷重を支持して運転されるとき、軸受の構造・機能により不可避的に転がり接触面に材料の疲労「転がり疲れ」が生じて、その後の継続使用ができなくなることがある。これと異なる経緯により寿命に達する以前に転がり疲れ以外の現象が生じて軸受の機能を失うことを「故障」と称して、転がり軸受では両者を区別している。 この「転がり疲れ」と「故障」を総称する用語として本書では「損傷」を使用し、これを他の事例にも広く適用した。一方、トライボロジーの分野では、先端的な加工機械や測定機器などのように、従来の機械及び機械要素の停止につながる「損傷」だけでなく、相対運動面のわずかな劣化等により目的とする高度の動的精度を達成することができなくなる場合にも、寿命として機械・機器類の作動停止を決断しなければならないことがある。「転がり疲れ」、「故障」、「損傷」と異なる使用限度の重要な要因である「機能低下」を本書で無視できない現象として扱った。これは精密測定器や顕微鏡等の観測手段で評価できない程度の劣化であるために、これまで「損傷」の部類に入れられなかったたぐいの不具合である。そこで、「機能低下」と「損傷」を総称する用語として「不具合」を本書で使用している。 本書の編集者・著者には現場のトライボロジー問題に通暁した方々に参画していただいた。本書を技術者の座右の書として常時手元に置いて利用してもらうことを期待し、図表の読みやすさや内容の充実を考慮して前書(「潤滑故障例とその対策」:1978年発行)のA5判から若干大きめのB5判とし、また損傷を実際に目で確認できるように、例示する図などは可能な限りカラーとした。

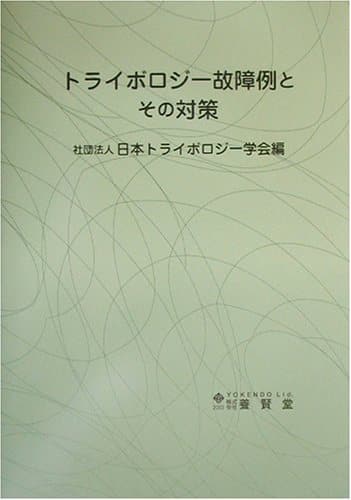











レビュー
レビューはまだありません。