目次
展望・総説・解説
コロナ禍における技術者倫理
慶應義塾大学 理工学部 機械工学科 教授
三木則尚
車載用リチウムイオン二次電池の現状と今後の展望
国立研究開発法人産業技術総合研究所
電池技術研究部門 蓄電デバイス研究グループ
総括研究主幹 研究グループ長
小林弘典
連載講座
データで学ぶ 超耐熱合金切削の基礎技術とトラブル対策(22)
第8章 セラミックス工具による高速・超高速切削
ものづくり人材育成塾 難削材切削技術研究所
狩野勝吉
CFDの基礎講座(35)
相転移のIsingモデルと数値解析 その1
慶應義塾大学 名誉教授
棚橋隆彦
詳しく学ぶ ねじ締結の基礎(24)
第4部 ねじ締結部の信頼性評価時の留意事項(4)
酒井ねじ締結相談室 室長 工学博士
日本機械学会フェロー
酒井智次
流体シミュレーション・ソフトウェア講座
Flowsquare+による数値熱流体力学(4)
Nora Scientific 代表
東京工業大学 工学院 助教
源 勇気
パリ協定以降の世界と日本のエネルギー動向(32)
水素エネルギー社会の課題と展望 その1
一般財団法人 航空宇宙技術振興財団 評議員
伊藤義康
コラム:一杯のコーヒーから(167)
Natural Intelligenceを活用しよう!―ControlからCoordinationへ
Stanford University visiting professor
慶應義塾大学 顧問
福田収一
新刊紹介
工学・工業界ニュース
説明
巻頭記事「コロナ禍における技術者倫理」
2020年の冬休みが終わる頃、中国の武漢市で原因不明の肺炎流行についてのニュースが流れた。NHKの特設サイトによると、1月14日にWHOが新型ウィルスを認め、1月16日には日本国内で初の感染が確認されている。とはいうものの、まだまだ危機感はなく、筆者もその次の週にフランスに出張している。空港や街中でも特に緊張した感はなかった。しかし帰国1週間後の1月30日にはWHOが「国際的な緊急事態宣言」を宣言。2月に入り、特にダイヤモンドプリンセス号の寄港の頃から、新型コロナウィルスがニュースにならない日がなくなった。
筆者の周りでは、卒業式や、恩師の最終公演が中止となった。3月上旬にはまだ卒業旅行に行く学生もいたが、終盤になると東京五輪・パラリンピックの延期が決定、例年の追いコンも中止。キャンパスが入構禁止になり、入学式も当然中止。春学期の開始が遅れることとなるも、オンライン授業の準備があわただしく始まった。4月の上旬に緊急事態宣言が出され、これは5月末まで解除されることはなかった。幸運なことに日本においては、第1波が無事に収束し、逆に経済への悪影響が多く取りざたされることとなった。
しかし、ヨーロッパを中心に新型コロナウィルス、COVID–19は猛威を振るい、各国で厳しいロックダウンがとられたにも関わらず、イタリアでは60歳以上の患者には人工呼吸器が使われない、など医療崩壊のニュースが流れ、3月下旬からは米国で急激に感染者が増加した。日本において感染が爆発しないのは、何らかの要因、ファクターXがあるのではないか、と願望も含めて、議論されるようになった。
本原稿を執筆している2020年10月現在、日本においては第2波も落ち着き、コロナウィルスに対する感染を制御しながらいかに経済を回すか、という方針が国民のコンセンサスを得ていると思われる。一方で、この秋から私の研究室に留学予定のスペイン、イタリア、フランスの留学生とオンラインで話をすると、日本よりも状況は深刻な印象を受けた。世界全体では収束はいまだみえず、日本においてもこれから冬にかけて感染が増えるのでは、という懸念は高い。本稿では、この未曽有の状況における技術者倫理について、多分に私見を交えながら議論してみたい。
慶應義塾大学 理工学部 機械工学科 教授
三木則尚
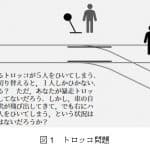
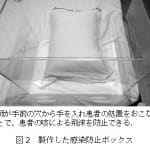
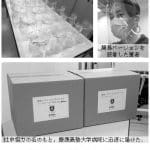
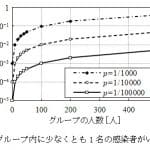


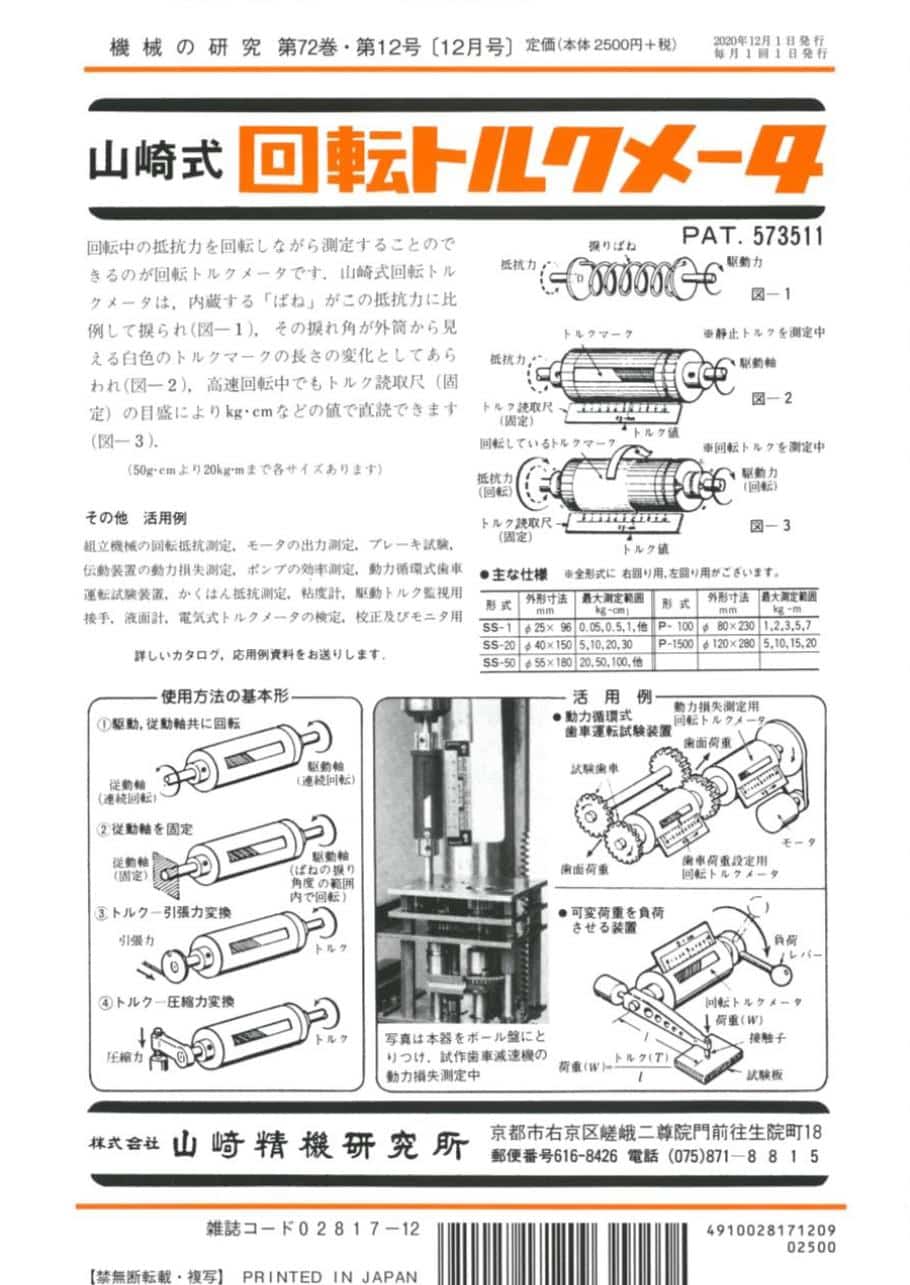
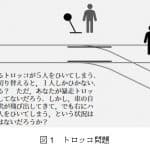
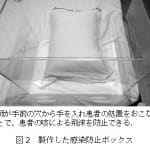
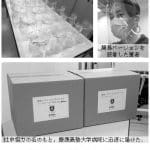
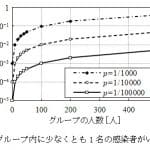















レビュー
レビューはまだありません。