目次
展望・総説・総論
円すいころ軸受の転動体荷重および寿命に関する実験的検討
公益財団法人 鉄道総合技術研究所
高橋 研
連載講座
カルマンフィルタとその周辺および応用(15)
確率システムの制御(2)
立命館大学 名誉教授
杉本末雄
大阪大学大学院工学研究科 特任准教授
和田光代
機械構造用金属材料の超高サイクル疲労(55)
7. VHCF-5~VHCF-7の10年間の研究動向(8)
立命館大学 名誉教授
酒井達雄
光ファイバー型赤外線輻射温度計の設計製作から計測まで(3)
光ファイバー型単色温度計の基本構造と特性
金沢大学 名誉教授
上田隆司
応用力学基礎講座(8)
誘電体・エマルジョン・磁性流体の力学への入門
慶應義塾大学 名誉教授
棚橋隆彦
自然環境と再生可能エネルギー(2)
東日本大震災と太陽光発電施設事例概報 その1
明治大学 再生可能エネルギー研究インスティテュート 客員研究員
飛田春雄
コラム:一杯のコーヒーから(198)
Softwarizationの時代 その2
元 Consulting Prof., Stanford Univ
慶應義塾大学 顧問
福田収一
特別講座:機械系大学院入試問題演習
(36)材料力学:東大2022年夏季実施より
(37)材料力学:東大2022年夏季実施より
神奈川大学 名誉教授
伊藤勝悦
歴史に学ぶ「機械の研究」
― 第6巻 第1号 掲載 特集「航空」図説・航空機の発達
新刊紹介
藤本,元,1940- 御牧,拓郎,1938- 植松,育三
出版社:森北出版
定価:2,600円+税
発売日:2025年7月12日
ISBN:978-4-627-66631-3
工学・工業界ニュース
説明
巻頭記事「円すいころ軸受の転動体荷重および寿命に関する実験的検討」
円すいころ軸受は建設、鉄鋼などの産業機械や自動車、鉄道車両などの交通機械において幅広く利用されている。鉄道車両においては、車軸の回転を支持する車軸軸受やモーターから輪軸に動力を伝達する歯車装置用の軸受として多く使用されている。軸受に荷重(軸に垂直方向のラジアル荷重や軸に平行方向のアキシアル荷重)が作用すると、軸受内部では転動体がその荷重を分担して、外輪と内輪に伝える。この荷重を転動体荷重、その分布を転動体荷重分布とよぶ。転動体荷重分布は軸受への荷重負荷方法や内部すきまによって変化し、転動疲労寿命に影響する。
軸受の転動疲労寿命の計算法はLundbergとPalmgrenの軸受寿命理論に基づいており、定格寿命は、軸受の基本負荷容量(動定格荷重)と等価荷重(動等価荷重)の比から求められる。この理論はその後の軸受の寿命計算法を規格化する際の基礎となり、日本でもJIS B 1518(転がり軸受の動定格荷重及び定格寿命の計算方法)として国内規格化されている。また、日本国内の鉄道車両用軸受については、日本鉄道車輛工業会規格JRIS J 0453(鉄道車両-車軸軸受の定格寿命計算方法)に車軸軸受の寿命計算法が上述のJIS規格に準じて定められている。これらいずれの規格においても、ラジアル軸受(主にラジアル荷重を支持する軸受)の場合、原則として負荷圏が円周上の半分である状態(すなわち、内部すきまが0である状態)を前提に動等価荷重を算出することとされているため、内部すきまが転動体荷重や軸受寿命に与える影響は、規格上は評価できない。
近年では、さまざまな取付条件下で使用される軸受に対して計算寿命と実際の寿命との乖離が指摘されるようになり、2008年に発行されたISO/R281の技術仕様書であるISO/TS16281では、ラジアル荷重とアキシアル荷重が作用する軸受に対して内部すきまと傾きを考慮したときの、力と変位の静的な釣り合いから求められる転動体荷重分布から動等価転動体荷重を計算し、修正軸受寿命を計算する方法が示されているものの、内部すきまと転動体荷重や軸受寿命の関係を実験的に検証した事例は少ない。
そこで、実物の円すいころ軸受を供試体として、その転動体荷重を動的に測定することにより、内部すきまの変化が転動体荷重分布に与える影響を調べるとともに、いくつかの内部すきまの条件下で、内部すきまが軸受のはく離やそれによって決定される軸受寿命に与える影響を調べた結果を本記事にて紹介する。
公益財団法人 鉄道総合技術研究所
高橋 研


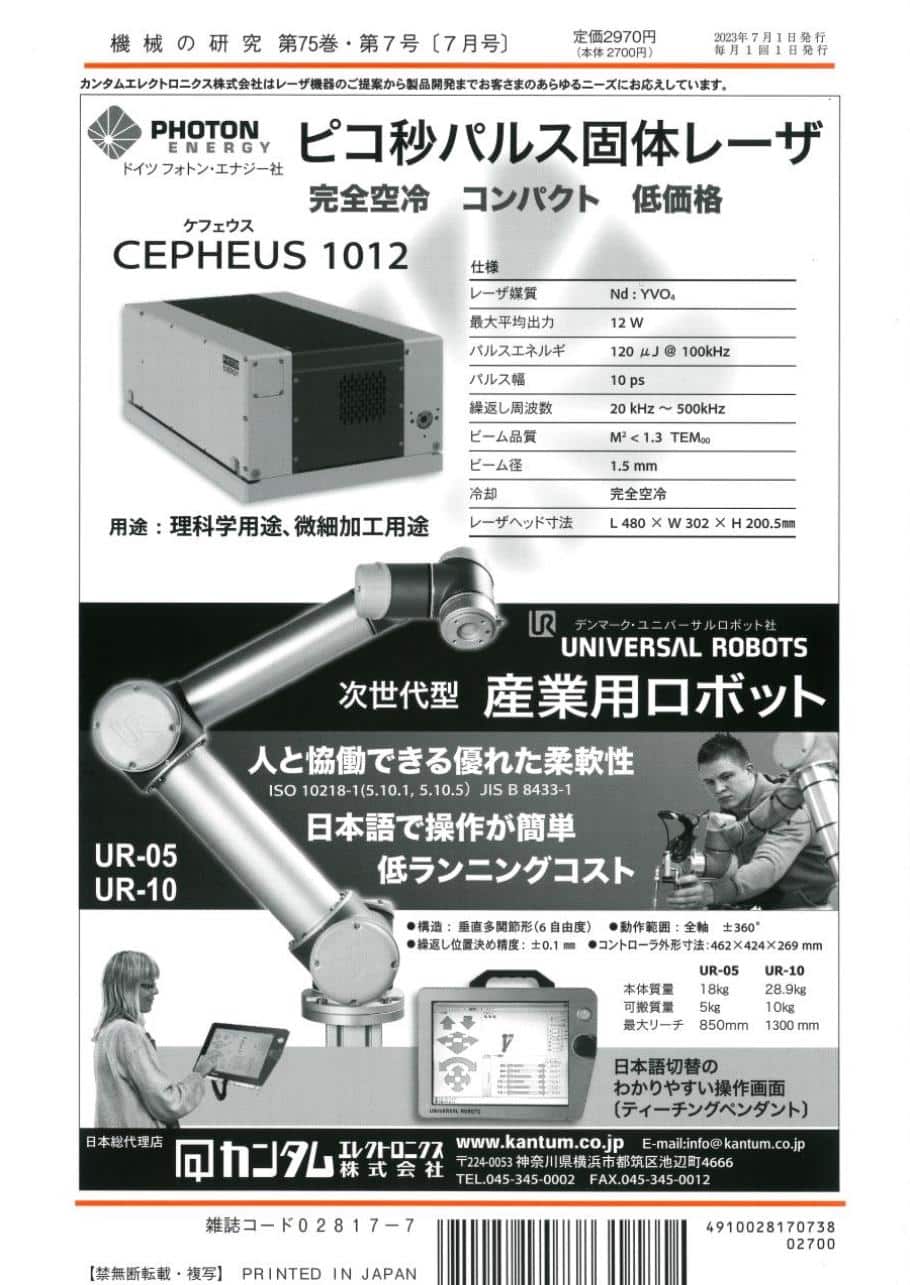
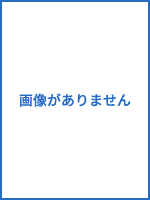















レビュー
レビューはまだありません。