目次
展望・総説・総論
熱弾性流体潤滑(材料特性の相違する場合)
九州工業大学 名誉教授
兼田楨宏
連載講座
カルマンフィルタとその周辺および応用(10)
カルマン・スムーザ(1)
立命館大学 名誉教授
杉本末雄
大阪大学大学院工学研究科 特任准教授
和田光代
応用力学基礎講座(3)
変分法の連続体への応用
慶應義塾大学 名誉教授
棚橋隆彦
植物の葉や花に関する力学的研究(9)
キュウリの体を支える巻きひげの力学的役割
(株)衝撃工学研究所 執行役員
大阪大学 名誉教授
小林秀敏
機械構造用金属材料の超高サイクル疲労(51)
7. VHCF-5~VHCF-7の10年間の研究動向(4)
立命館大学 名誉教授
酒井達雄
コラム:一杯のコーヒーから(193)
機械工学によるGuerilla Marketing その2
元 Consulting Prof., Stanford Univ
慶應義塾大学 顧問
福田収一
特別講座:機械系大学院入試問題演習
(30)材料力学:東工大2021年夏季実施より
神奈川大学 名誉教授
伊藤勝悦
歴史に学ぶ「機械の研究」―第23巻 第1号 掲載 特集「流体工学」
工学・工業界ニュース
説明
巻頭記事「熱弾性流体潤滑(材料特性の相違する場合)」
重要かつ代表的な機械要素である集中接触面をもつ転がり軸受や歯車などの機能・性能・信頼性向上の一翼を担うトライボロジーの一分野である弾性流体潤滑(Elastohydrodynamic Lubrication, EHL または EHD と略称される)は、油膜厚さ形状の数値解析結果とその実時間直接観測を可能にした光干渉法を両輪として 1960 年代に確立された。その後、新たな数値解析法の開発、潤滑油特性、潤滑油の接触域内流動特性や表面粗さの影響など多岐にわたる事項が検討されその潤滑現象の理解が高められつつある。
同一平滑面同士が等温下で接触する場合の一般的特徴はつぎのようにまとめられる。
- 接触域の大部分で膜厚はほぼ一様であり、潤滑油の出口付近の膜厚の低下(くびれ)が発生する。くびれ発生開始位置で圧力は増加してピークを呈した後低下する。
- 接触中央域ならびに最小膜厚は \(U\)、\(G\)、\(W\) によって評価できる。
- \(U\) および \(G\) の評価に必要な粘度および粘度の圧力係数は潤滑油の接触域流入部の温度で規定できる。
しかし、上記とは全く相違する特異現象が 1990 年代に純滑り EHL 運動下で観察され、膜厚方向に変化する温度つまり粘度の変化に起因することが明らかにされた。すなわち、熱伝導率の高い物体が静止して熱伝導率の低い物体が運動する場合には接触域に膜厚の局所増加(ディンプル)が発生し、その部分の圧力は増加する。しかし、逆の場合には膜厚の局所増加は発生しない。
運動方向の接触領域が増加すると膜厚の局所増加の数は増加する。
ディンプルの発生が接触二物体の熱伝導率の差に依存するとの事実は、集中接触する機械要素の EHL 現象に大きい影響を与えると考えられ、EHL 現象の解明には温度の影響を考慮することが必要不可欠となる。また、多くの熱的・機械的特性の相違する材料の存在と開発を考慮すれば、それらを集中接触材料として使用する可能性を排除することはできない。そこで、本稿では筆者のグループの成果をもとに、熱的•機械的特性の相違する材料を集中接触部材として使用した場合に発生する EHL 現象の基本事項を明らかにする。
九州工業大学 名誉教授
兼田楨宏


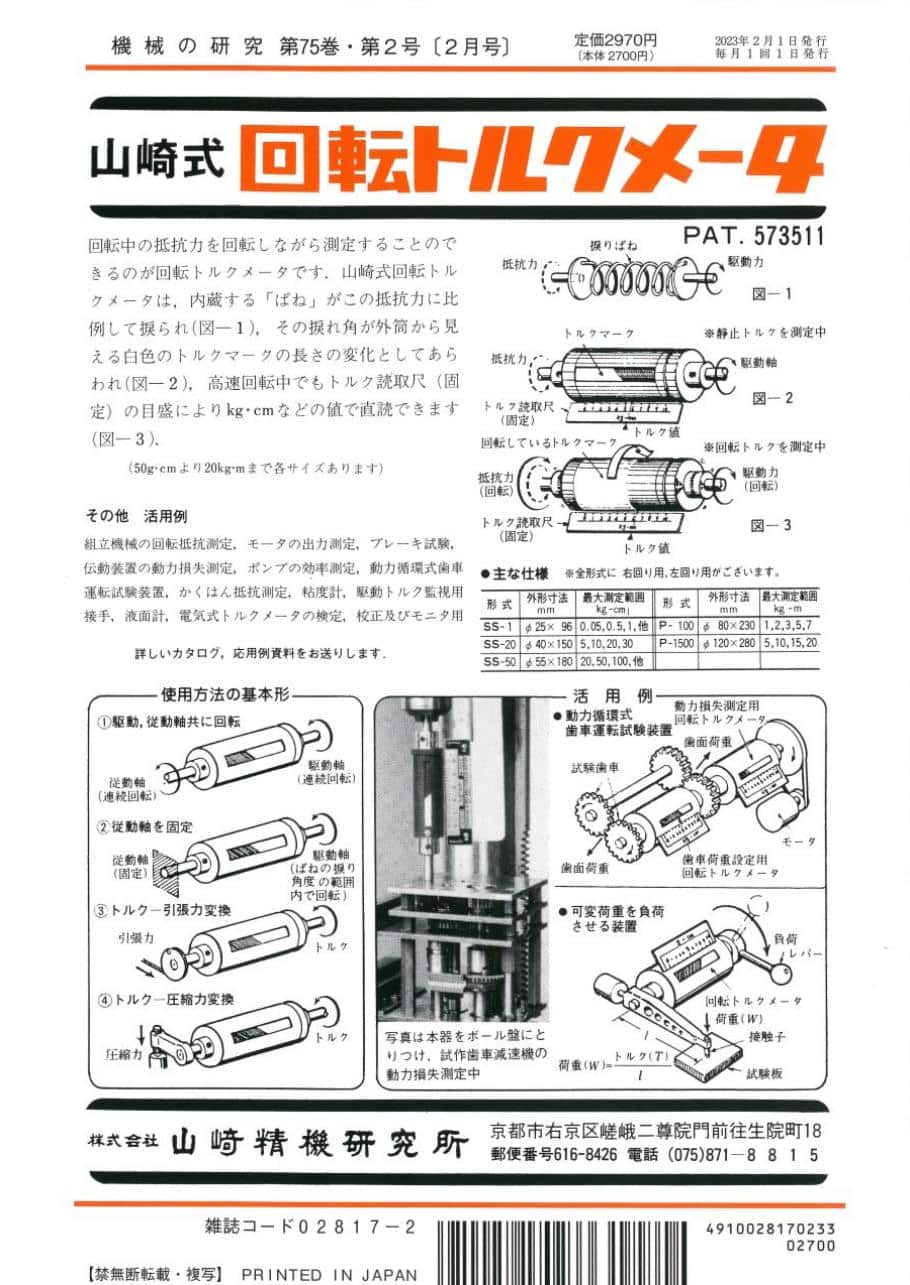















レビュー
レビューはまだありません。