目次
第1章 総論
第2章 農業水利施設の整備の歴史と情勢変化
1)農業水利施設の整備状況
2)社会共通資本としての農業水利施設
3)農業・農村の変ぼうと環境の変化
4)農業水利の高度化への取組み
5)農業水利施設の役割と展望
第3章 性能照査の取組みとマネジメント技術
1)農業水利施設の特性と機能
2)農業水利施設の性能設計
3)農業水利施設の性能管理とマネジメント技術
第4章 農業水利施設の機能診断・補修・補強の技術とリスク管理
1)機能診断技術の現状と今後の技術開発
2)性能の低下予測技術の向上
3)補修・補強技術の選定手法
4)ライフサイクルコスト評価手法
5)農業水利施設のリスク管理
第5章 マネジメントのための情報化技術と体制
1)農業水利ストック情報データベース
2)用水路システムデータベース
3)GISを活用したパイプライン事業地区履歴管理データベース
4)情報化研究の方向
第6章 マネジメント工学と社会経済システム
1)土地改良法と事業制度
2)マネジメント事業の経済評価
3)ストックマネジメントにおける合意形成
4)ソーシャルキャピタルと農業生産基盤の地域共同管理
― 社会工学的アプロ-チ ―
5)農業水利施設の外部経済とマネジメント工学
第7章 農業水利施設のマネジメント工学の構築に向けて
1)農業水利施設のサイクルマネジメント
2)農業水利施設のアセットマネジメントへの展開
3)計画設計基準へのマネジメント工学の導入
4)マネジメント工学の確立に向けて
索引
説明
食料供給力にとって最も基礎的な資源である農業用水を、農地に供給している全国の農業用水路の延長は約40万km、うち受益面積100ha以上の基幹的水路は約4万7,000kmにもおよぶ。また、貯水池や頭首工などの基幹的な取水施設は約7,000カ所、この他にため池が大小合わせて21万カ所存在し、ため池を除くこれら農業水利施設の総資産額は約25兆円と見積もられている。日本はその位置、地形、地質、気象および水象などの自然条件から、地震、台風、集中豪雨などの自然災害に対し脆弱な国土となっている。この上に国民の生活を支える社会基盤が築かれ稠密な社会経済が営まれている。たとえば、日本の国土面積は全世界の0.25%に過ぎないが、全世界における過去5年間の自然災害による被害額の約13%を日本が占め、その中で農林水産業関係が約50%となっている。また、国土の約40%は農業生産に不利で災害が発生しやすい火山灰性粘性土や軟弱地盤であり、これらの点は欧米先進国と決定的に異なる国土条件である。
一方、現在の日本の食料自給率(カロリーベース)は、40%と先進国の中でも極めて低い水準にある。さらに、農村地域では人口減少・高齢化が進展し、産業・生活両面にわたる活力低下や国土保全、水資源涵養、自然環境保全などの多面的機能の低下の問題が生じている。また、地球温暖化に伴う気候変動は、人間の生存基盤そのものに影響を与えることが懸念されている。これらを考えると農業水利施設の保全管理・更新整備は、安全で質の高い農村や安定的な食料確保に基づく国民生活を実現するための基盤として不可欠なものである。
このような状況のもと、国民生活と農村の基盤を支える大規模かつ重要な社会インフラの機能診断、老朽化や耐震に対応する補修・補強、農業や社会のニーズに即した施設のアップグレード、効率的な更新整備などのためのマネジメントに関する技術開発は、すぐれて国民の共通利益につながるものであり、地域と国全体の双方の見地に立って考えるべき課題である。また、少子高齢化・人口減少社会の到来や厳しい財政制約の中で、社会にとってできる限り少ない費用負担で農業水利施設の保全管理をしていくためには、予防保全対策などにより施設の長寿命化を図るなど、ライフサイクルコストが最小となるよう計画的なマネジメントを推進することが重要となっている。
農村工学研究所では、これまで「管理の時代」に対応して農業水利施設の機能診断(劣化と損傷の検知・計測・診断・劣化予測・リスクマネジメント)、施設の整備を効率的に行うための補修・補強工法、耐久性向上やコスト縮減のための設計・施工・メンテナンス技術、性能照査手法などの施設の保全管理・更新整備に関するさまざまな技術開発に取り組んできている。
本書は、それらの成果を関係技術者、学生および一般の読者に広く紹介し、活用を図るとともに「農業水利施設のマネジメント工学」の構築に向けて農業・農村の将来を見据え、技術開発から社会経済システムまでの多方面から取り組むべき技術戦略について取りまとめたものである。

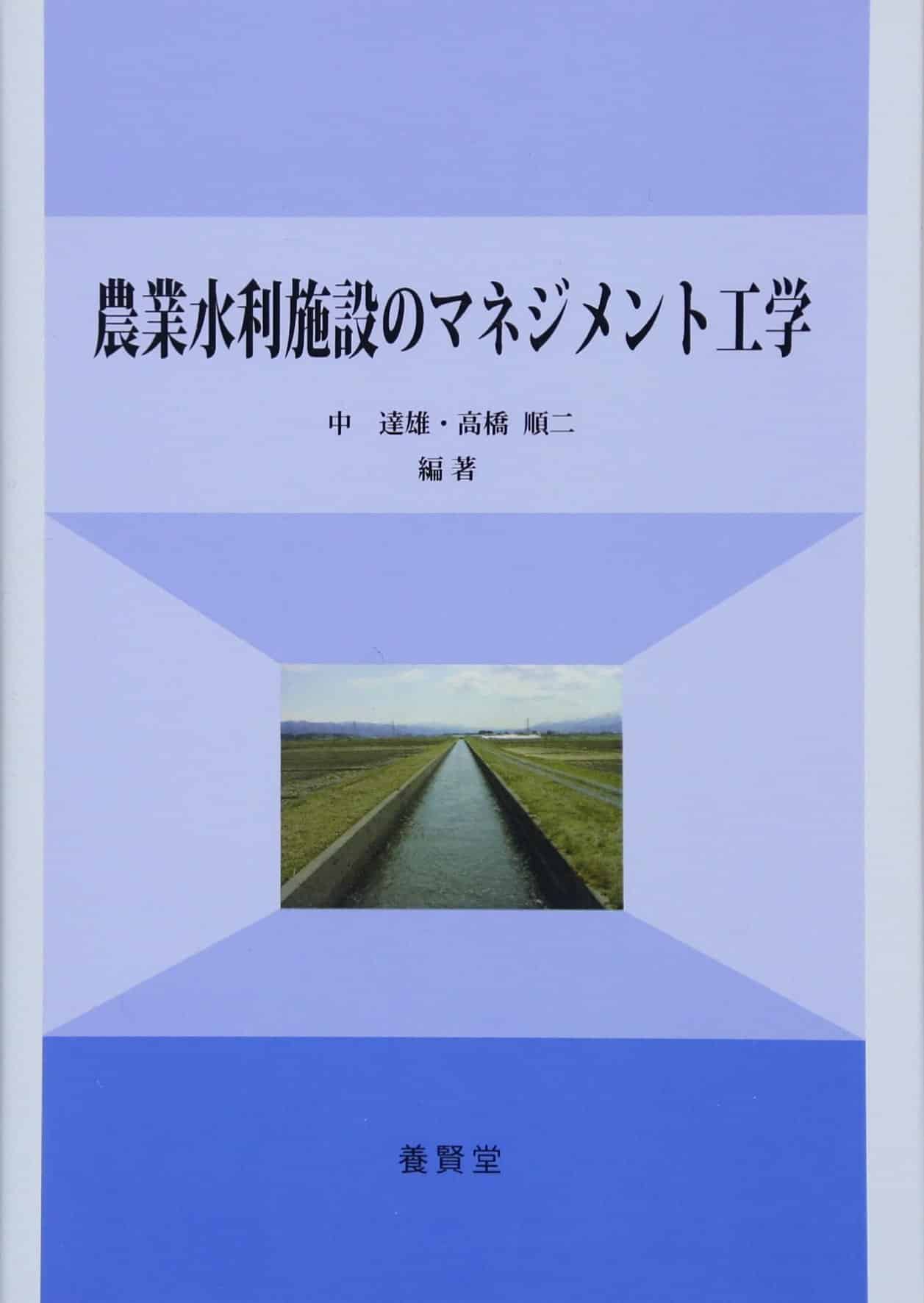
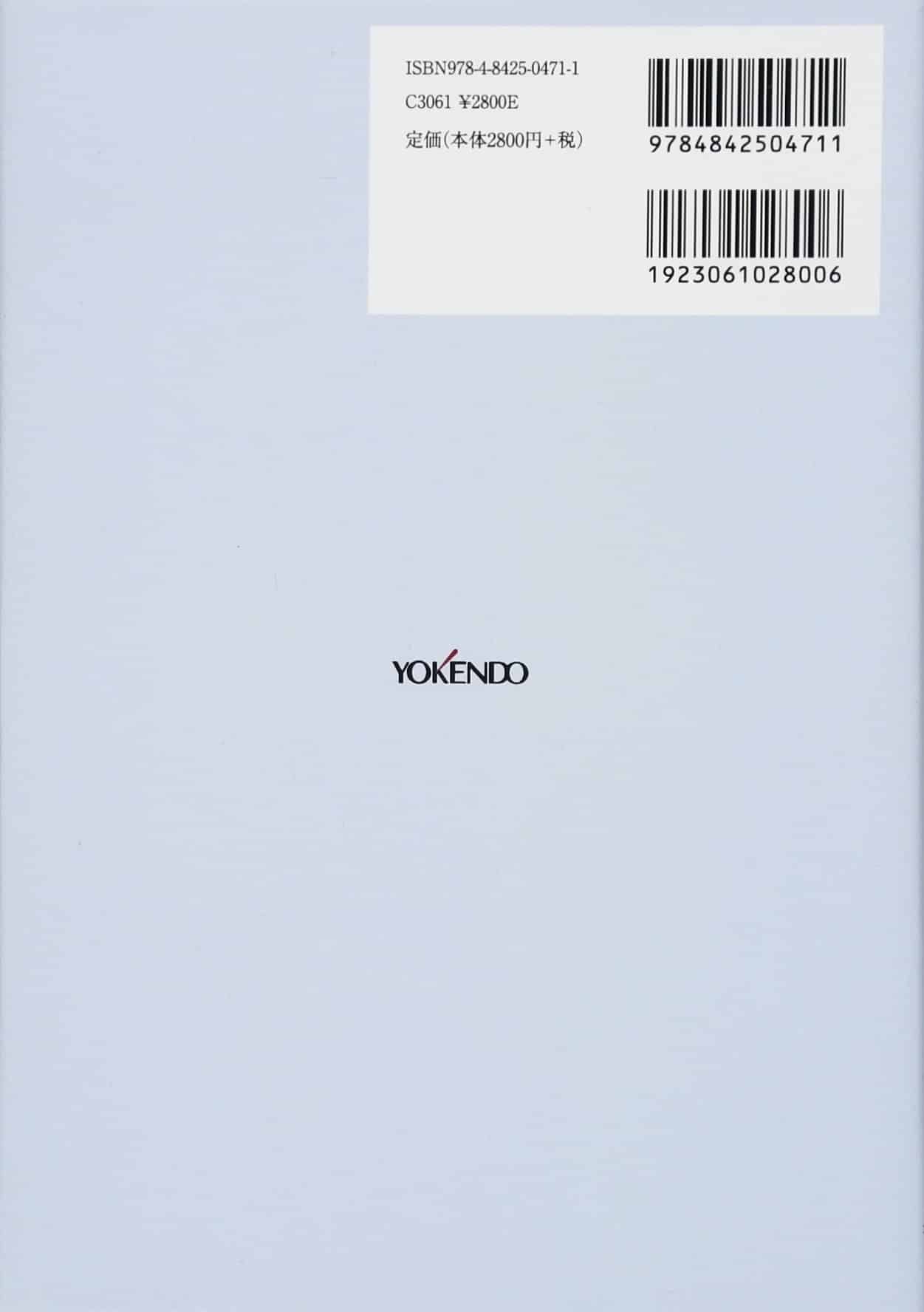

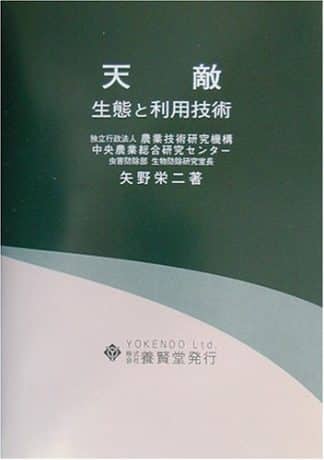
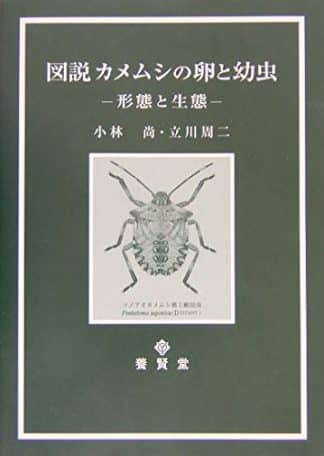










レビュー
レビューはまだありません。