目次
1章 研削加工の概要
1.研削加工の定義と位置づけ
2.研削加工の特徴
3.研削作業の分類
2章 研削砥石
1. 研削砥石の3要素と5因子
2.砥粒
3.結合剤の種類と結合度
4.組織
5.砥石の回転破壊強さ
3章 研削仕上げ面粗さ
1.研削仕上げ面粗さ創成の理論
2.粗さの理論式における諸問題
4章 研削機構
1.砥粒切込み深さと砥粒切削長さ
2.三次元砥石モデルに基づいた理論式
5章 研削抵抗
1.研削抵抗の理論式
2.比研削抵抗の寸法効果
3.研削抵抗の測定)
6章 砥石のドレッシングとツルーイング
1.ドレッシングとツルーイングの意味
2.通常砥石のドレッシング
3.超砥粒砥石のツルーイングとドレッシング
7章 砥石の摩耗と自生作用
1.砥石の摩耗と寿命
2.砥粒切れ刃の自生作用
3.レジンボンドダイヤモンド砥石における砥粒の埋没現象
4.骨材砥粒の摩耗
8章 新しい研削技術
1.クリープフィード研削
2.超高速研削
3.超精密鏡面研削
4.非球面研削
5.平面ホーニング
説明
研削加工は、いろいろな点で切削加工と研磨加工の中間的な位置づけにある。しかしそれでいて、最近、特に研削加工に対する期待が大きいのは、両翼にある二つの加工が共有し得ない優れた特質を備えているためであろう。そして何よりも、研削加工は他の二つの加工に比べて、加工変数が多い。これは、取りも直さずこの加工が未完成であるということを示しており、技術的にはノウハウに属するものが多く、発展の可能性をより多く秘めているということでもある。これが、この加工への期待度を高めているともいえるのではないだろうか。
本書は、できるだけ研削現象をモデル化することによって、体系的に理解し得るような記述を心掛けた。本書では、SEM(走査型電子顕微鏡)の写真を用いて砥石表面を立体視する手法を取り入れ、できるだけ読者と情報を共有するようにした。立体写真は、対になる2枚の写真の間に厚手の白紙を立てて左右の目でそれぞれの写真を見つめることにより、誰でも簡単に立体視できる。おっくうがらずに、ぜひ試みていただきたい。
「学問」は、文字によって、その内容を100%読者に伝えることができる。しかし「技術」の場合は、文字によって、100%伝えることは不可能である。著者は、それが「技術」の本質であると考えている。つまり、文字によって伝えられるのは、「技術」の方向性だけであって、「技術」の本質ではない。文字や言葉では伝えられない「技術」の本質は、それぞれが体得しなければならないものであり、これがいわゆるノウハウである。
われわれ研究者は、文字や言葉では伝えられない「技術」の本質を、「技能」として、より低く位置づけてきた嫌いがある。それが生産技術者に伝染し、生産技術者が「技術」の本質を見失いノウハウの蓄積を軽視したことが、わが国における生産の空洞化の一因となったのではないだろうか。
本書は、大学院程度の学生や研削加工に関する知識をさらに深めようとする技術者、研究者の教科書を念頭に置いている。したがって、基本的に、広く受け容れられていると思われる内容を主にしている。
(序文より)

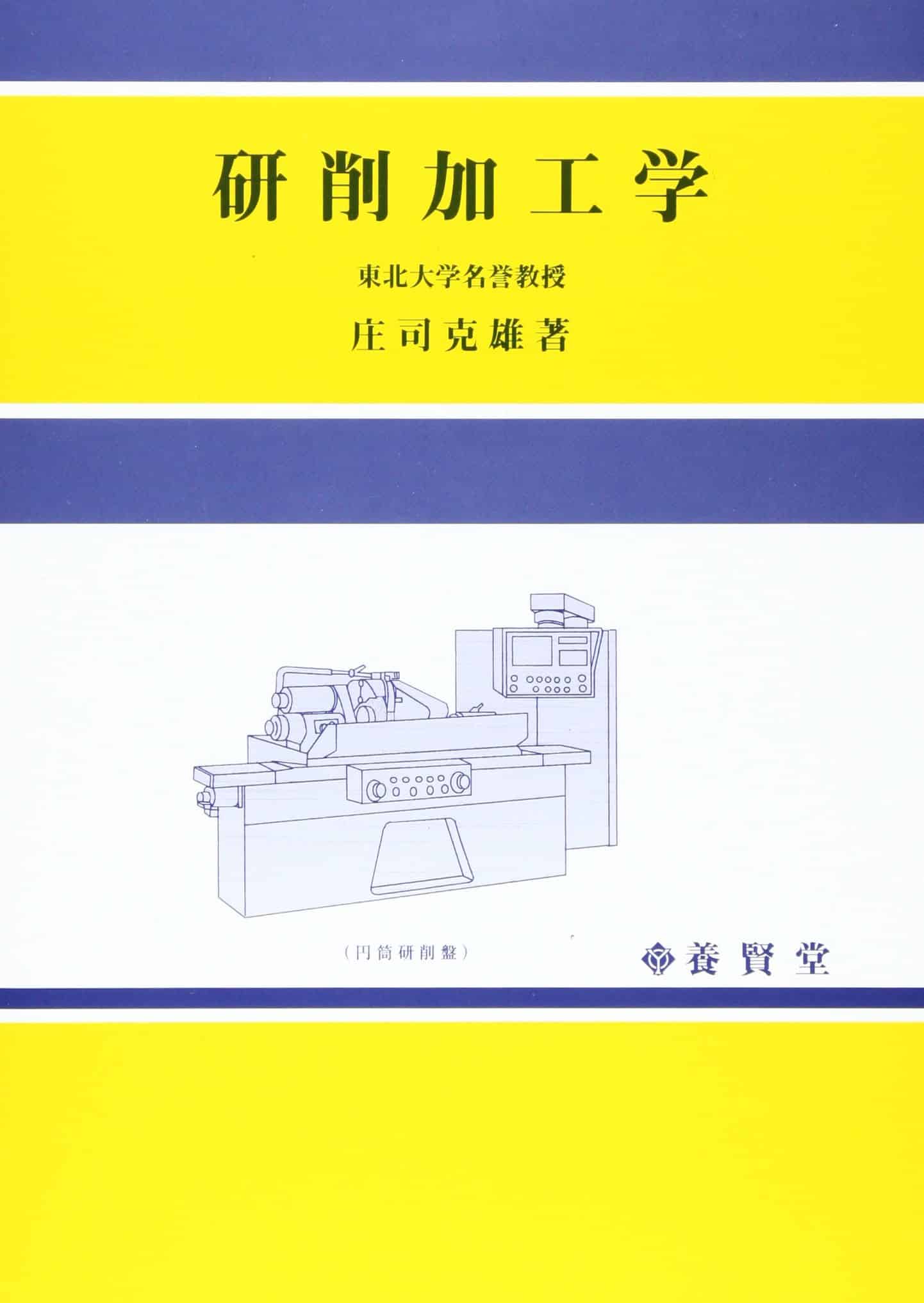


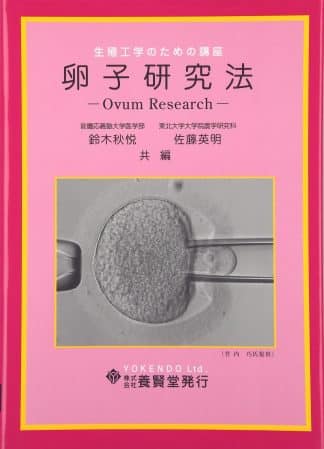










レビュー
レビューはまだありません。