目次
展望・総説・解説
生物規範型ソフトロボット
(中央大学 理工学部 精密機械学科 助教)
奥井 学
(中央大学 理工学部 精密機械学科 教授)
中村 太郎
技術士の紹介
―技術者の活躍をサポートする国家資格―
(TNKT 技術士事務所 所長)
(技術士 (機械部門、綜合技術監理部門))
田中 建夫
連載講座
詳しく学ぶ ねじ締結の基礎(9)
(酒井ねじ締結相談室 室長 工学博士・日本機械学会フェロー)
酒井智次
産業安全工学(27)
本質安全と安全率
(有明工業高等専門学校 創造工学科 教授)
堀田源治
サウンドデザイン論(6)
―音をデザインし製品価値を高めるには―
(広島市立大学 教授)
石光俊介
データで学ぶ 超耐熱合金切削の基礎技術とトラブル対策(11)
―旋削加工の基礎技術(3)―
(ものづくり人材育成塾 難削材切削技術研究所)
狩野勝吉
パリ協定以降の世界と日本のエネルギー動向(21)
新エネルギー基本計画
(トーカロ株式会社 顧問)
伊藤義康
CFDの基礎講座(23)
状態方程式と遷移行列 その2
(慶應義塾大学 名誉教授)
棚橋隆彦
コラム:一杯のコーヒーから(155)
ICBBD, ICEPS, ICESI, TSHF Joint International Conference 2019(その1)
(Stanford University visiting professor、慶應義塾大学 顧問)
福田収一
新刊紹介
工学・工業界ニュース
総目次
説明
巻頭記事「生物規範型ソフトロボット」
ソフトロボットが注目を集めている。
ソフトロボットにおいて生物規範の考えは広く用いられるが、その位置づけ、すなわち「生物の何を規範とするか」の考え方は多様である。
ソフトロボットというワードが登場してから1990年代ごろまでは、ソフトロボットはソフトなハードウェア研究を指すことが多かったそうである。
すなわち、柔らかいアクチュエータや柔らかい構造のロボットへの活用であった。そのためこの頃のソフトロボットにおける生物規範は、生物の持つ機能的な柔らかさを模倣し、制御では対応しきれない突発的、規定不能な外乱を構造で吸収する、という意味合いであった。
特に人間との接触に対してならうように変形するため安全であるという点が強調されており、コンプライアンスを持つアクチュエータをうまく制御したり、新しいソフトアクチュエータそのものを開発したりする、という研究が多数であった。
一方で生物は、構造系と制御系が美しく融合し、既存のロボットでは実現できないさまざまな動きを実現している。
たとえば昆虫の飛翔時には、筋肉配置、軽くしなやかな羽の構造、外骨格の適度な変形などのさまざまな要素が統合され機能する。
人間がものをつかむ際も、筋肉の冗長的な駆動系、皮膚感覚の活用、視覚による位置フィードバックなどが統合的に働く。
このような、環境に対する構造・制御の統合的進化は、生物が長い年月をかけ獲得したものである。
現在のソフトロボットにおいては、構造的な生物規範に加えて、このような環境・構造・制御の統合的な機能を模倣しようという考えが浸透している。
これはPfeiferが2000年ごろに提唱した身体性や、鈴森が提唱するE-Kagenといった現代ソフトロボティクスのキーワードにも表れている。
これらの流れからわかるように、ソフトロボットにおける生物規範ではやみくもに柔らかさを付加すればよいわけではない。
そのような形態となっている理由を環境や制御と合わせて学び、そのエッセンスをロボットに応用すべきである。
本稿では、当研究室で開発しているソフトロボットを題材に、開発事例を紹介する。
(中央大学 理工学部 精密機械学科 助教)奥井 学
(中央大学 理工学部 精密機械学科 教授)中村 太郎
ピックアップ「技術士の紹介 ―技術者の活躍をサポートする国家資格―」
技術士という資格は技術者にとって最上位に位置付けられた国家資格であると考えられている。
それでは技術士とはどんな技術者のことをいうのだろうか。
技術士法第二条は『技術士とは登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術(人文科学のみに係るものを除く)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く)を行う者』と記している。
本稿では技術士について知って頂くため、技術士制度の始まりからの変遷、技術士になるための試験、技術士が持つべき資質能力(コンピテンシー)、日本技術士会の体制、その中の一部会で筆者が所属する機械部会の体制と活動内容を述べる。
最後に、技術士がより活躍するために必要なことは何か、筆者が考えていることも含めて述べる。
技術士および その制度について知って頂くとともに、技術士になりたいと思って頂ければ幸いである。
(TNKT 技術士事務所 所長)
(技術士 (機械部門、綜合技術監理部門))
田中 建夫


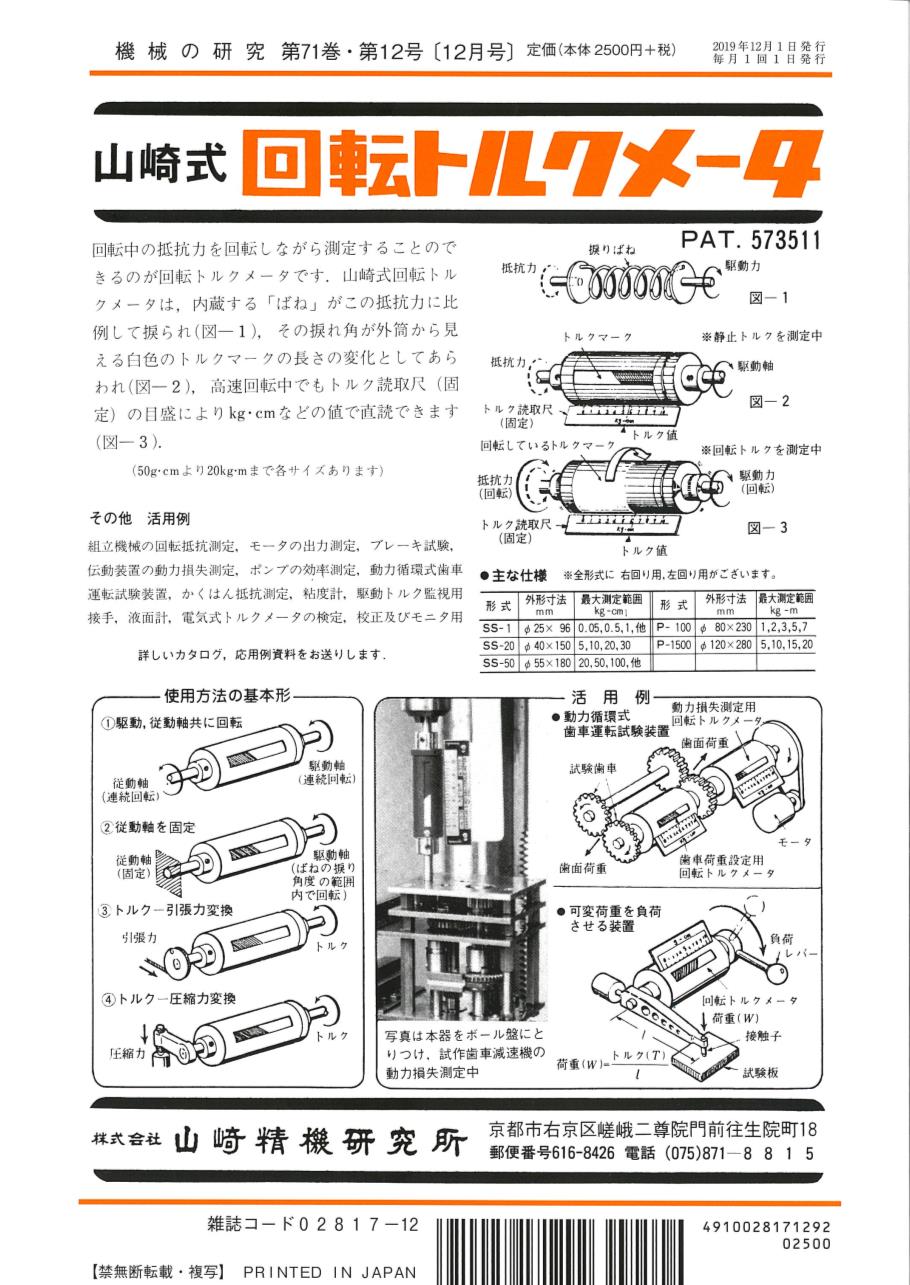




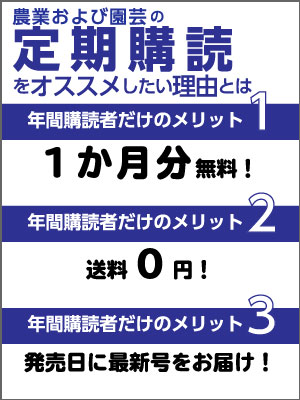










レビュー
レビューはまだありません。