目次
第1章 地球環境への理解
1.1 人口増加と環境への影響
1.2 大気・水・土壌汚染の現状
1.3 地球温暖化と熱汚染
1.4 酸性雨とオゾン層の破壊
1.5 廃棄物による環境破壊
第2章 エネルギーの種類と賦存量
2.1 過去・現在・未来のエネルギー
2.2 再生可能なエネルギー
2.3 再生できないエネルギー
2.4 エネルギー資源の賦存量
2.5 新エネルギーへの期待
第3章 エネルギー消費の現状
3.1 民生用エネルギー
3.2 輸送用エネルギー
3.3 生産用エネルギー
3.4 エネルギー消費と二酸化炭素排出
第4章 地球環境保全への考え方
4.1 二酸化炭素削減への配慮
4.2 エネルギーリサイクルの効果
4.3 エネルギーシステムの再構築
4.4 水素エネルギーへの対応
4.5 廃棄物リサイクルの効果
4.6 二酸化炭素半減への対応と可能性
第5章生活に密着した考え方
5.1 環境に優しいエネルギー技術
5.2 室内環境への対応
5.3 地域エネルギーグリッドの構想
5.4 再生可能なエネルギーの活用
参考文献
索引
説明
本書は、エネルギー利用と地球環境への正しい知識を得るための考え方を示したもので、興味を持っていただける方々、小学校・中学校・高等学校の先生方、大学・高等専門学校での一般教育を受けている学生の方々などを対象に執筆しております。したがって、基礎となる事項から重要なエネルギー・環境に関連する事項を紹介して、例を挙げて考え方を理解していただくよう考慮するとともに、とかく誤解しやすい自然エネルギー利用への限界を知るため、大気汚染・水汚染・土壌汚染のほかに、熱汚染への問題点も示しました。また、地球温暖化の原因として化石燃料の消費により発生する二酸化炭素の効果が挙げられていますが、大気中の水蒸気や亜酸化窒素も同様の効果があります。その大気中の二酸化炭素や水蒸気を取り去ると、地球平均温度が現在の15℃から-18℃に低下するといわれており、地球環境への考え方の難しさもあるのです。
従来の考え方にとらわれず、エネルギー・環境への理解を助けるため、また、将来を見据えての指針が得られるよう、次の点を考慮しております。
(1)地球環境への対応として、大気汚染、水汚染、土壌汚染のほかに熱汚染のあることを示し、化石燃料、核エネルギー、自然エネルギー消費による熱汚染への危惧を知っていただくことにしました。
(2)大気中の二酸化炭素や水蒸気などは、地球温暖化の効果はあるものの、現在の地球平均温度を保つ重要な役割も果たしていることを示し、環境への考え方の難しさを知っていただくことにしております。
(3)一般に、エネルギー統計は、化石燃料、核エネルギー、自然エネルギーを網羅していますが、熱エネルギーあるいは電気エネルギーという違う形態で表す場合もあります。また、エネルギー資源の賦存量についても、種類によって異なる単位で表すことが普通であり、統一見解を難しくしています。したがって、エネルギーおよび資源の種類にかかわらず、熱エネルギーの単位で表すことにしたのです。
(4)エネルギー消費に際して相当量の排熱が放出されていますが、最近の技術革新によりリサイクルが可能となっています。したがって、排熱も一種のエネルギーと考え、エネルギー資源に加算することにしています。
(5)自然エネルギーとしての太陽光エネルギーについては、賦存量を調べて利用できる可能性を示すとともに、水力、風力、バイオマスへの転換後についても利用できる可能性を推定することにより、その重要性を認識していただくよう考慮しています。
(6)化石燃料、核エネルギー、自然エネルギーによる電力発生の効率を考えますと、統一した取扱いがないための誤解があり、水力や風力に比べて太陽光、バイオマス、化石燃料、核エネルギーによる電力発生の効率が極めて低い値として示されています。したがって、電力発生の技術に関する正しい知識が得られず、将来への指針を誤ることになるので、統一した効率への概念を紹介して参考に供することにしました。
(7)従来の環境への考え方に室内環境の論議が欠けていましたが、生活の大半を過ごす室内環境の重要性を示して、建材からの汚染物質、コンクリートに含有されるラドンなどの放射性物質、人から放出される二酸化炭素による汚染への対策を紹介しています。さらに、しばしば社会問題となっている室内での一酸化炭素中毒への対策として、例えば省エネルギー型のFF暖房機の効用を示すとともに、室内環境を保つ換気の必要性を知っていただくことにしました。
(8)積雪寒冷地におけるエネルギー資源としての氷雪利用について紹介し、寒冷環境による氷温エネルギーの利用への考え方を知っていただくことにより、自然エネルギーの新しい取組みへの期待が高まればと考えています。
(9)最近の地球環境に関する話題となっている二酸化炭素半減への対応について検討し、将来の動向を予測しながら可能性を探ることが望まれています。したがって、そのために必要な考え方を理解し、対処していただきたいと思っています。
ただちに、エネルギー・環境に関連する専門知識を理解することは難しいとしても、本書で記述した考え方を学ぶことにより、望ましいエネルギー利用と地球環境に関する新しい展開が可能になると思います。また、室内環境への知識を理解することによって、快適な生活を送るための指針を得ていただきたいと考えています。紙面の制約から、十分意を尽くすことができなかった箇所もあると思いますが、読者の方々からご意見をいただき、将来補足する機会が得られれば幸いです。

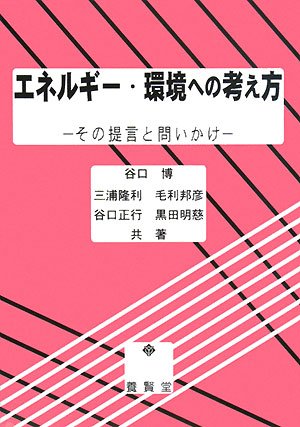













レビュー
レビューはまだありません。